[掲載 2020年12月16日] [更新 2024年05月20日] |
| 日本は文字文化の国 | |
| 動作確認等 | - |
| 01_文字の実体 - 知識の蓄積 |
文字には、画像同様、物理的な実体はありません。実際、文字符号化方式の規格文書では、図形という用語が使用されています。文字そのものを運搬、保存することはできません。文字は、物理的な実体がある「紙」などの媒体に書いたり印刷すれば、その媒体と共に移動でき、保存できます。 ところで皆さん、下図の文字は何と読むと思いますか ? |
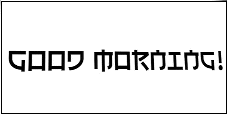 |
図1 何て読む ? |
| 02_表音文字・表語文字・表意文字 |
我々人類の祖先であるホモ・サピエンスが現れたのは約 20 万年前、人類が言葉を使うようになったのは 7 万年程前、文字が誕生したのは、5,000 ~ 6,000 年前とされています。 原始的な文字は絵文字でした。つまり、文字は絵から始まったことになります。おそらく、数を数えるのが目的で絵を描き始めたのではないかと思われています。そのうち、絵と絵を組み合わせて言葉を絵にするようになり、文字が増えていきました。エジプトで生まれたピエログリフは 、1,500 ~ 2,000 文字あったようですが、簡略化されて原カナン文字 (シナイ文字) になり、更に形を変え、フェニキア文字となり、やがてヨーロッパに伝わりアルファベットとなりました。アルファベットのように、音だけを表すのを「表音文字」と言います。 中国でも、甲骨文字と呼ばれる絵文字が生まれ、漢字という文字に変化していきました。中国の漢字を取り入れた日本では更に、ひらがな、カタカナという仮名文字が生まれました。 表音文字は音だけを表し、1 字だけでは意味を持ちません。しかし、表音文字というシステムは、文字を組み合わせてどんな単語、言葉でも書けます。表音文字が生まれたのは画期的と言えます。表語文字では、単語、言葉の分だけ文字が必要になり、文字の数が増えていきました。実際、考古学的な文字、表音文字を含めて、現在 18 万以上の文字があるとされていますが、その大半は表語文字の漢字です。 |
| 03_日本は文字文化 ( 漢字文化 ) の国 |
日本は漢字文化の国です。坂本龍馬などの手紙や文書ではひらがなも使用されていますが、明治維新までの武士の社会では、公文書は当然、手紙も漢字だけでした。いわゆる候文です。明治になって、公文書にもカタカナが使われるようになりましたが、ひらがなは「女文字」と呼ばれ、嫌われていたようです。その名残りは太平洋戦争が終わるまで続いています。公文書などでひらがなが使われるようになったのは戦後です。 例えば、アメノカは亜米利加、イギリスは英吉利です。これらは、「夜露死苦 (ヨロシク)」と同じで、いわゆる当て字ですが、これらの漢字は表音文字として使われていたことになります。これは、同じ漢字文化の中国でも同じです。 現在の日本では、人の名前に当て字が使用できます。例えば「宇宙」の漢字で登録されている名前には、ウチュウ、ソラ、コスモ、ハルカ、ヒロシ、タカヒロ、等があります。 |
アメノカ (
亜米利加 → 米国 ) アメリカ ( 美利堅合衆國 → 美国 ) |
日本は、仮名という独自の表音文字を創り出し、それを表語文字と組み合わせて使用する独自の文字文化を築いてきました。以下は、日本の文字の豊かさを示す例です。同じ言葉でも、カタカナだけ、ひらがなだけ、漢字を使用した場合とでは、読み手が受け取る印象が変わってきます。漢字を使うと深みというか、重みのようなものを感じるようになります。 |
オイシイ |
同じ発音でも、使用する漢字によっても印象が変わることがあります。「めぐり合う」と「めくり逢う」などはその例と言えます。「逢う」の方が何となくロマンチックを感じます。 明治の文豪と言われる作家の作品は、漢字をふんだんに使用していて、意味深で重厚感があります。最近の作家の中には、ひらがなを積極的に使用して、必要で重要と思われるところだけを漢字にする方もいます。そのほうがメリハリがあるとも言います。 |
| 04_文字の読み書きには意図的な学習が必要 |
人は、生まれると、やがて、自然と学習して言葉を話すようになります。しかし、文字はそうはいきません。人の脳には、最初から文字を読み書きする能力があるわけではありません。意図的に学習しないと文字の読み書きはできません。そめためには、文字を何度も声を出して読み、音からも記憶します。同じ文字を何度も繰り返し書くことによって「文字」を覚えるという練習が必要です。声に出して読むというのは重要です。脳は、文字を読む時に音声に変換するからです。 文字を習い始めた、ほとんどの子供に共通した間違いがあります。それは、以下のような鏡文字と呼ばれる左右が逆向きの文字を書くことです。これは世界共通の現象です。この現象は、自然なこととされています。 成人でも、病気やケガをすると、一過性ですが、鏡文字を書くことがあることが知られています。 |
| にんじん けんちくし り → り ん → ん ご → ご け → け く → く |
人が文字を読む時、脳の視覚野という場所で文字の形を認識します。側頭頭頂移行部という場所で、文字の形を手掛かりに音に変換します。更に、言語野という場所で、話し言葉や思考にかかわる情報を処理します。これらが同時に複雑に働いて文字を認識していることが分かっています。 脳は、この大変な処理を簡略化して、省エネ作業を行います。それを自動化するために、脳は、ビジュアル・ワード・フォームエリア と呼ばれる場所を使用します。ここは顔の形の認識にも使われている場所です。視野の中心のパーツを使用して情報を取り出し、全体の形として一瞬で認識します。この省エネ処理は、顔や文字に限ったことではありません。一般的な脳の機能です。 次のような文字を 1 秒間だけ見せて、書いてある文字を当てるテストがあります。ほとんどの人が最初の文字を「ヘリコプター」と答えます。実際には コ と プ が逆順になっています。いわゆる早トチリです。これが脳の省エネ処理の結果です。文字単位ではなく、文字全体として認識した結果です。 |
| ヘリプコター みさなん、こんちには ! メソポタアミ文明 マカロニグタラン アンドメロダ銀河 |
本ページ最初の画像の文字は、GOOD MORNING! です。脳の省エネ処理が働いて、英語圏の人は難なく読めるそうですが、カタカナを知っている日本人は、カタカナを連想してしまうようです。 文字の読み書きが苦手な人がいます。文字が読めても書くのが苦手な人もいます。 ディスレクシアは、英語圏ては調査が行われていて、人口の 10% ~ 15% 程度いるとされています。日本では、ある小学校の調査では、該当する児童が 8% ~ 9% いたという報告があります。 |
文字が使われ始めてから 5,000 ~ 6,000 年と言われていますが、長い間、文字は、権力者や上流階級の人々のものでした。その結果、格差が生まれ、知識や知恵がある者に従わざるを得ないという状況になります。それが権力者達にとって都合が良かったからではないかと歴史家はみています。 今から 150 ~ 160年程前、幕末から明治維新の時代、多くの外国の人達が日本に来て、日本と日本人についての記録を残しています。それらの中に、日本人の識字率の高さに驚いたという記述があります。当時のイギリス国民の識字率は 15% ~ 20% 程度でしたが、日本人の識字率は約 75% でした。世界的にも珍しい高い識字率だったことは間違いないようです。 コンピュータは、文字そのものを記憶したり保存することはできませんが、人の脳は、文字を図形パターンとして記憶して保存しているのかも知れません。 |
[備考] |