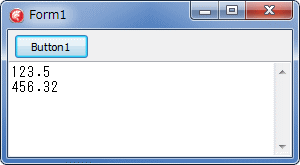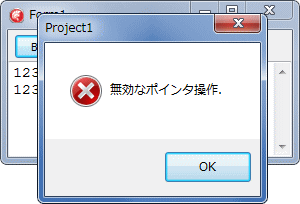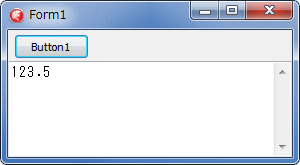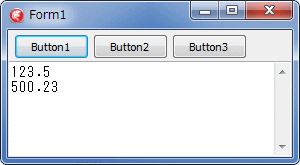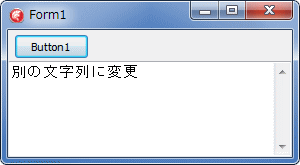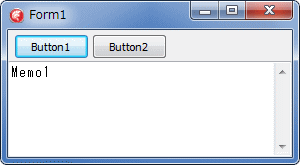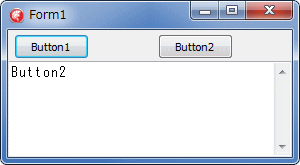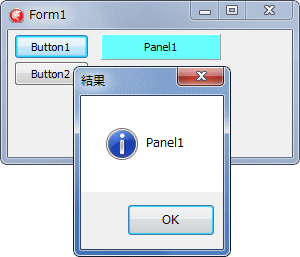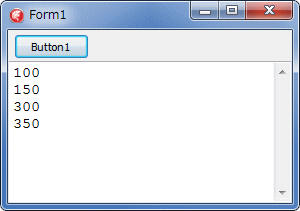Delphi Programming / Object Pascal Delphi 一般・その他
ポインタとポインタ型
動作確認等
Windows 7 U64(SP1) + Delphi XE5(UP2) Pro VCL-32
プログラムで使用する変数の値 (データ) は全てメモリに書き込まれます。データが書き込まれるメモリ上の位置をメモリアドレス、あるいは単にアドレスと言います。
一般的にオブジェクトの操作では、メモリブロックのコピーを作成して処理が行われます。メモリブロックのコピーを作成しないでオブジェクトを操作する変数の型があります。それがポインタ型です。ポインタ型の変数は、メモリ上のデータを直接操作することになります。そのため、ポインタ型を使用すると処理が高速になります。
ポインタ型の変数はメモリのデータを直接操作しますから、ポインタとしてのアドレスが意味を持ちます。例えば、関数や手続きの引数に渡す時は「アドレス渡し」になります。一方、ポインタ型ではない変数の場合は、メモリブロックのコピーを使用しますから、アドレスという概念てははなく、その変数の値による操作となります。関数や手続きの引数では「値渡し」となります。
ポインタ型を使用した方が便利なことがあります。ポインタ型のプロパティを持つクラスもあります。Delphi の型には、多くの型にそのポインタ型が用意されています。型名の前に大文字の P があるのがポインタ型です。ポインタ型が用意されていない型でも、型宣言することでポインタ型を使用するこができます。
[備考 1]-
[備考 2]-
ポインタ型の変数に @ 演算子付きの変数を代入すると、そのポインタ型の変数は、アドレスの情報と変数の型情報を持つポインタとなります。
ポインタ型の変数からメモリのデータを取得したり、メモリにデータを書き込むには、逆参照と言う手法を使用します。ポインタ型の変数の末尾に記号 ^ (ハット・キャレット) を追加すると逆参照となります。ポインタ型の変数には、変数のデータが書き込まれているメモリ領域 (メモリブロック) の先頭アドレスの値が格納されています。逆参照は、そのメモリアドレスのデータを直接操作することを意味します。これをポインタの逆参照と
言っています。
以下のサンプルコードは、ポインタ型の変数にメモリ上のアドレスをポインタとして代入して、逆参照で元の値を取得する例です。
図1
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LSrcValue : Double;
LDstValue : Double;
LpDouble : PDouble;
begin Memo1.Lines.Clear;
LSrcValue := 123.5 ;
// 変数の型に応じたポインタ型の変数に代入// Double 型のポインタとなる// このポインタはアドレスと型情報を持つLpDouble := @LSrcValue;
// ポインタが示すアドレスに書き込まれているデータを逆参照で取得LDstValue := LpDouble^;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LDstValue));
// 逆参照でポインタが示すアドレスに値をセット// 元の変数の値も変わるLpDouble^ := 456.32 ;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LSrcValue));
end ;
動的配列等、変数がポインタの時は、メモリを確保する処理が必要です。ポインタ型の変数もポインタですからメモリの確保が必要です。
上のサンプルコードは、代入元の変数のデータに対してポインタ型の機能を利用する例です。
以下は、データを格納するメモリを確保してポインタ型の変数を使用する例です。つまり、他の変数とはメモリを共有しないで、独立したポインタ型の変数として使用する場合です。
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LpDouble : PDouble;
LDstValue : Double;
begin Memo1.Lines.Clear;
New(LpDouble);
try LpDouble^ := 123.5 ;
// 逆参照でポインタ型の変数の値を代入LDstValue := LpDouble^;
// ポインタが示すアドレスの値を逆参照で取得LDstValue := LpDouble^;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LDstValue));
// 逆参照でポインタが示すアドレスに値をセットLpDouble^ := 456.32 ;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LDstValue));
// メモリを確保したポインタ型の変数には他の変数のアドレスを代入しないこと// 代入は可能だがポインタ型の変数のデータの格納アドレスが変わってしまう// その結果、確保したアドレスのメモリが解放できなくなる// 確保したメモリの解放後であれば代入しても構わない// LpDouble := @LDstValue;finally Dispose(LpDouble);
end ;end ;
メモリを確保したたポインタ型の変数に値を代入したり、別の変数にポインタ型の変数の値を代入するには逆参照を使用します。@ 演算子を付けた変数を代入したりすると、確保したメモリアドレス以外の場所にデータが格納されてしまいます。代入はできても、確保したメモリの解放ができなくなりメモリリークが発生することになります。
図2
ローカル変数は初期化されません。以下のコードは PDouble 型の変数用のメモリを確保していませんが、実行しても例外は発生しません。
これは、いわゆる「ゴミ」による結果です。初期化していないメモリには不規則な値が書き込まれています。当然、ポインタ自身のアドレスにもあります。単純型の変数である Double 型の変数はどんなバイト値でも 8 バイトを数値として読み取れます。書き込み先のメモリも、変更されても問題ない場合は書き込めます。
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LpValue : PDouble;
LValue : Double;
begin LpValue^ := 123.5 ;
LValue := LpValue^;
end ;
前項のサンプルで使用したポインタ型は、変数の型に応じたポインタ型でした。 Pointer 型という型情報を持たない汎用のポインタ型があります。この型の変数はアドレス情報だけを持つポインタです。@ 演算子を付けた変数は汎用のポインタと同じですが、型情報を持つポインタ型の変数に代入した場合、そのポインタ型の変数は、型情報はそのままでアドレス情報だけが変更されます。
汎用のポインタも、元のポインタ型でキャストすれば、その型のポインタ型の変数に代入したり逆参照できます。Pointer 型の変数には型情報がありません。型キャストすることによって、アドレスに書き込まれているデータを取得てきます。以下はその例です。
図3
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LSrcValue : Double;
LDstValue : Double;
LPointer : Pointer;
begin LSrcValue := 123.5 ;
// 汎用のポインタ型の変数にアドレスをセット// 汎用のポインタとなる// 結果的に LPointer := Addr(LSrcValue); と同じになるLPointer := @LSrcValue;
// 元のポインタ型でキャストして逆参照するLDstValue := PDouble(LPointer)^;
Memo1.Lines.Text := FloatToStr(LDstValue);
end ;
数値型の変数等、ポインタ型の変数ではない変数を関数や手続きの引数に渡すと。その変数の値は、元の変数と関数や手続き内部では別のメモリ上のアドレスに書き込まれます。つまり、関数や手続き内部ではそれらの変数を独立して操作できるようになっています。
引数の変数の前に予約語 var を付けると、その変数は、関数内部でも元の変数と同じメモリ上のアドレスを使用するようになります。つまり、その引数に対する関数内部での処理結果を呼び出し側で受け取ることになります。この時この引数を「変数パラメータ」と言います。このような引数の渡し方を「参照渡し」あるいは「var 渡し」とか「アドレス渡し」と言っています。
引数がポインタ型等の変数の場合、関数の呼び出し側と難数内部でポインタが示すアドレスが変わることはありません。これは var を付けた変数と同じで「参照渡し」です。データを書き込む時はポインタが示すアドレスに書き込まれ、ポインタが示すアドレスからデータが読み出されます。
0
図4
最初の値は手続きを実行する前の変数の値
次が手続きを実行した後の変数の値
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// ポインタ型の引数を持つ手続きの例// -----------------------------------------------------------------------------procedure TestProc(ApValue: PDouble);begin ApValue^ := 500.23 ;
end ;// =============================================================================// テスト用の手続きを使用する例// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
begin Memo1.Lines.Clear;
LValue := 123.5 ;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LValue));
TestProc(@LValue);
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LValue));
end ;// =============================================================================// テスト用の手続きを使用する例// メモリを確保してポインタ型の変数を使用する例// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LpValue : PDouble;
begin Memo1.Lines.Clear;
New(LpValue);
try LpValue^ := 123.5 ;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LpValue^));
TestProc(LpValue);
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LpValue^));
finally Dispose(LpValue);
end ;end ;// =============================================================================// テスト用の手続きを使用する例// 汎用のポインタ型 (アドレス情報のみ) を引数に渡す場合// 結果の取得には型キャストが必要// =============================================================================procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
LPointer : Pointer;
begin Memo1.Lines.Clear;
LValue := 123.5 ;
LPointer := @LValue;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LValue));
TestProc(LPointer);
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(PDouble(LPointer)^));
end ;
以下のように、引数の型が汎用の Pointer の時は関数内部では必要な型として処理することになります。関数を利用する側は元々何かの型のデータとして処理しますから、引数がポインタとしてのアドレス情報だけを持っている汎用の Pointer型でも処理可能です。
// -----------------------------------------------------------------------------// 汎用のポインタ型の引数を持つの手続きの例// -----------------------------------------------------------------------------procedure TestProc(ApValue: Pointer);begin PDouble(ApValue)^ := 500.23 ;
end ;
作成する関数を次のようにすれば汎用性が高くなります。関数を使用する側では、汎用のポインタ型の変数でも、型情報付きのポインタ型の変数のどちらでも引数として使用できます。
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// 汎用のポインタ型の引数を持つの手続きの例// 汎用性の高いコード// // (1) 引数の型を処理する対象の型のポインタ型にする// (2) 引数の処理はそのポインタ型でキャストしてから逆参照する// -----------------------------------------------------------------------------procedure TestProc(ApValue: PDouble);begin PDouble(ApValue)^ := 500.23 ;
end ;
[備考 1]
[備考 2]
次のサンプルで使用している関数の引数には予約語の var がありません。しかし、手続き内部で操作した結果が呼び出し側で取得できています。
このサンプルの手続きの引数は、TStringList というクラス型の変数です。
図5
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// クラス型の引数の内容を処理する手続きの例// 引数には参照渡しの予約語 (変数パラメータ) var がない// -----------------------------------------------------------------------------procedure TestProc(AList: TStringList);begin AList[0 ] := '別の文字列に変更' ;
end ;// =============================================================================// 上の手続きを使用するコード// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LStrList : TStringList;
begin Memo1.Lines.Clear;
LStrList := TStringList.Create;
try LStrList.Add('テスト文字列' );
// 手続き実行TestProc(LStrList);
// 手続き内部で変更した値となるMemo1.Lines.Add(LStrList[0 ]);
finally FreeAndNil(LStrList);
end ;end ;
Delphi では TObject を使用してクラス型のデータの受け渡しが可能です。Delphi のクラス型の変数はポインタです。
TObject 型の変数にクラス型の変数 (オブジェクト) を代入します。TObject はメモリアドレスの情報だけを保持するポインタです。TObject はクラスの型情報を持ちません。TObject 型のポインタから元のオブジェクト (変数の内容) を取得する時は、元のクラス型でキャストします。そうすると、引数が示すアドレスのメモリのデータを、そのクラス型のデータとして使用できるようになります。
図6
図7
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LObject : TObject;
LButton : TButton;
begin Memo1.Lines.Clear;
LObject := Button2;
LButton := TButton(LObject);
LButton.Left := 150 ;
Memo1.Lines.Add(LButton.Caption);
end ;
TButton 等のイベントに TOject 型の引数があります。以下はその TObject 型の引数を使用した例です。上のサンプルコードはこの TObject の使用方法と同じです。
Button1C2ick メソッドの引数は TObject 型です。TObject 型の変数には、オブジェクトのデータが格納されている (書き込まれている) メモリの先頭アドレスの情報しかありません。TPanel で型キャストすることにより、メモリのデータを TPanel のデータとして取得します。当然ですが、TObject が示すアドレスには TPanel のデータが格納されているわけですから、他のクラス型でキャストしても正しい結果は取得できません。例外が発生することがあります・
Delphi のクラスでは、TObject がクラス型の汎用ポインタと言えます。
図8
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);begin Button2Click(Panel1);
end ;procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LPanel : TPanel;
begin LPanel := TPanel(Sender);
MessageBox(Handle, PChar(LPanel.Caption), '結果' , MB_ICONINFORMATION);
end ;
07_ 汎用ポインタとしての TObject 型と Pointer 型
これまでのテストで確認したように、Delphi では、TObject がクラス型の汎用ポインタと言えます。
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);begin TestProc(Panel1);
end ;procedure TForm1.TestProc(Sender: Pointer);var LPanel : TPanel;
begin LPanel := TPanel(Sender);
MessageBox(Handle, PChar(LPanel.Caption), '結果' , MB_ICONINFORMATION);
end ;
クラス型の変数を扱うのに、上のように Pointer 型を使用する必要はありませんが、TBitmap の場合でも、次のように TObject 型と Pointer 型を使用して処理できます。クラス型のオブジェクトをポインタr 型の変数に代入する際、@ 演算子付きで代した場合は、逆参照が必要です。
このサンプルは、クラス型のオブジェクトをポインタ型や TObject 型を使用して処理する必要がある場合を想定したテストです。
図9
copy code
// =============================================================================// クラス型のオブジェクトをポインタ型の変数に代入する例// // Pointer 型の変数に @ 演算子付きで代入// ポインタ型の変数からオブジェクトを取得するには逆参照が必要// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LBitmap : TBitmap;
LDstBitmap : TBitmap;
LPointer : Pointer;
begin Image1.Picture.Assign(nil );
LBitmap := TBitmap.Create;
try LBitmap.LoadFromFile('503.bmp' );
// Pointer に @ 演算子を付けて代入LPointer := @LBitmap;
// ポインタから TBitamap を取得// 逆参照が必要LDstBitmap := TBitmap(LPointer^);
Image1.Canvas.Draw(0 , 0 , LDstBitmap);
finally FreeAndNil(LBitmap);
end ;end ;// =============================================================================// クラス型のオブジェクトをポインタ型の変数に代入する例// // Pointer 型の変数に @ 演算子なしで代入// ポインタ型の変数からオブジェクトを取得する時に逆参照記号は不要// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LBitmap : TBitmap;
LDstBitmap : TBitmap;
LPointer : Pointer;
begin Image1.Picture.Assign(nil );
LBitmap := TBitmap.Create;
try LBitmap.LoadFromFile('503.bmp' );
// Pointer 型に @ 演算子なしで代入LPointer := LBitmap;
// ポインタから TBitamap を取得// 逆参照は不要LDstBitmap := TBitmap(LPointer);
Image1.Canvas.Draw(0 , 0 , LDstBitmap);
finally FreeAndNil(LBitmap);
end ;end ;// =============================================================================// クラス型のオブジェクトを TObject 型の変数に代入する例// クラス型変数の特性を使用する最も確実と思われるな方法// // 汎用ポインタとしての TObject 型の変数に @ 演算子なしで代入// TObject 型の変数からオブジェクトを取得する時に逆参照は不要// =============================================================================procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);var LBitmap : TBitmap;
LDstBitmap : TBitmap;
LObject : TObject;
begin Image1.Picture.Assign(nil );
LBitmap := TBitmap.Create;
try LBitmap.LoadFromFile('503.bmp' );
// TObjcet 型の変数に @ 演算子なしで代入// これは LObject := TObject(LBitmap); と同じ意味LObject := LBitmap;
// ポインタから TBitamap を取得// 逆参照は不要LDstBitmap := TBitmap(LObject);
Image1.Canvas.Draw(0 , 0 , LDstBitmap);
finally FreeAndNil(LBitmap);
end ;end ;// =============================================================================// クラス型のオブジェクトを TObject 型の変数に代入する例// // 汎用ポインタとしての TObject 型の変数に @ 演算子付きで代入// TObject 型の変数からオブジェクトを取得するには Pointer でキャストして逆参照する// =============================================================================procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);var LBitmap : TBitmap;
LDstBitmap : TBitmap;
LObject : TObject;
begin Image1.Picture.Assign(nil );
LBitmap := TBitmap.Create;
try LBitmap.LoadFromFile('503.bmp' );
// TObject 型の変数に @ 演算子付きで代入LObject := @LBitmap;
// TObject 型の変数から TBitamap を取得// Pointer でキャストしてから逆参照が必要LDstBitmap := TBitmap(Pointer(LObject)^);
Image1.Canvas.Draw(0 , 0 , LDstBitmap);
finally FreeAndNil(LBitmap);
end ;end ;
Delphi のクラス型の変数はポインタですから、クラス型のポインタ型を使用する機会はあまりないかも知れませんが、クラス型もポインタ型を宣言できます。
copy code
type // ポインタ型を定義PBitmap = ^TBitmap;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LBitmap : TBitmap;
LpBitmap : PBitmap;
LDstBitmap : TBitmap;
LPointer : Pointer;
begin LBitmap := TBitmap.Create;
try LBitmap.LoadFromFile('503.bmp' );
// ポインタ型の変数に代入LpBitmap := @LBitmap;
// 逆参照で元のクラス型のオブジェクトを取得LDstBitmap := LpBitmap^;
Image1.Canvas.Draw(0 , 0 , LDstBitmap);
finally FreeAndNil(LBitmap);
end ;end ;
ポインタ型は、クラス型に限らず、次のように、変数の宣言時でも設定できます。型名の先頭に ^ (キャレット) を追加するだけです。
copy code
// =============================================================================// ポインタ型は、変数は宣言時でも宣言が可能// ポインタ型の変数と他の変数とでメモリを共有する場合// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
LpValue : ^Double;
begin Memo1.Lines.Clear;
LValue := 123.5 ;
LpValue := @LValue;
LValue := 500.5 ;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(Lpvalue^));
end ;// =============================================================================// ポインタ型は、変数の宣言時でも宣言が可能// ポインタ型の変数を独立した変数にする場合// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
LpValue : ^Double;
begin Memo1.Lines.Clear;
New(LpValue);
TRY LValue := 123.5 ;
LpValue^ := LValue;
LValue := 500.5 ;
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(Lpvalue^));
finally Dispose(LpValue);
end ;end ;
[備考]
Delphi のレコード型はポインタ型ではありませんが、ポインタ型も定義されています。
以下のリンクの記事に、メモリを確保して、レコード型のポインタ型の変数を、独立したポインタ型の変数として操作する例があります。
図10
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LRect : TRect;
LDstRect : TRect;
LpRect : PRect;
begin Memo1.Lines.Clear;
// テスト用データLRect := Rect(100 , 150 , 300 , 350 );
// レコード型のポインタ型の変数にレコード型変数のアドレスを代入LpRect := @LRect;
// 逆参照で元のレコード型変数のデータを取得LDstRect := LpRect^;
// 取得結果を表示Memo1.Lines.Add(IntToStr(LDstRect.Left));
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LDstRect.Top));
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LDstRect.Right));
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LDstRect.Bottom));
end ;
[備考]
10_ 汎用ポインタ型の Objects プロパティと Data プロパティ
TListView 等、項目をリスト操作するコントロールには、TListItem 型のクラスを使用して各項目にインデックスでアクセスします。この TListItem には Data という名前の Pointer 型のプロパティが実装されててます。
Pointer はポインタ型の汎用ポインタで、TObject はクラス型の汎用のポインタですから、数値型、レコード型、クラス型等のポインタ型の変数を代入できます。リストの項目にそれらのポインタ型の変数を代入すると、リストの各項目が固有のデータを持つことになり機能を拡張できます。
Objects プロパティや Data プロパティに代入するのはポインタとしてのアドレスだけです。したがって、それらのプロパティの操作には TObject 等によるキャスト、あるいは逆参照を使用します。ポインタ型の変数を使用するには、そのポインタ型の変数のメモリの確保と解放処理が必要です。