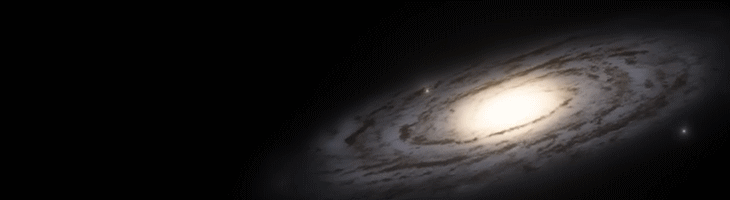
小説 : 空飛ぶ地球人 伊豆 大若
じいさんとの出会い
「お前さん、空を飛んでみたいと思わないかい ?」
じいさんは言った。
次村 誠 (ツギムラ マコト) は 50 歳を過ぎていた。勤務先の施設内にある診療所の診療放射線技師だ。本来の仕事の他にも、パソコンに詳しいと言う理由で、新たに赴任してきた課長と、転職してきた数人の事務職の人達に頼まれて、パソコンで使用する業務関係のアプリの開発も行っていた。
当時、職場にはパソコンは一台もなかった。新たに赴任してきた課長が導入を決めたのである、誠はパソコン購入の担当にさせられた。
誠が務める機関では年間を通じて、パート職員の手を借りる多くの行事が催されている。正規職員の給与関係の処理はホストコンピュータによって行われていたが、パート職員の賃金の処理は、事務の人が電卓と集計表という用紙を使用して手作業で処理されていた。
開発したアプリの効果は絶大だった。毎日の処理は不要になり、月末に勤務表の内容を入力するだけになった。この作業は 1 時間程で十分だった。手書きで 4 日間もかかった年末の源泉徴収票の作成は、プリンタが自動で印刷するようになった。30 分も待てば印刷は終了する。
このことが契機になつて、官公庁関係への報告書や診療関係の業務アプリの開発の依頼が増えていった。
部署内にパソコンが増えてくると「LAN を組むと便利だ」と言う者が現れた。余計なことを言うやつだ。結局、部署内サーバを置くことになり誠が担当者にされて、予算が足りないということで LAN 工事も行った。インターネットを利用する提案もあったが、誠は反対した。当時はインターネット接続の電話料金は従量制だった。業務アプリの開発ほとんど自宅でやっていたが、開発、つまりプログラミング関係の情報はインターネットで得ていた。接続時間が長い月には、電話会社から確認の電話を受けたことが何回もあったのだ。もし職場でインターネット接続するとなると、相当の出費となる可能性があると思ったからである。
やがて IT 化の波が押し寄せてきた。情報管理部門が設置され、組織全体のサーバが設置されたが、実際の管理は外部委託となった。パソコンの OS と機種が統一されクラウド化されていった。個人が作成したプログラム類の使用は禁止され、これまで開発した業務アプリは使用できなくなったのである。業務アプリで処理していた作業は表計算ソフトや文書作成ソフトで行うことになったが、それらのソフトによる処理は、手作業で行っていた時よりも時間がかかるようになった。まずは、それらのソフトの使用方法にどを習得しなければないらい。開発という重圧から解放されたが、今度は、それらのソフトの使用方法などを教える立場になってしまった。
業務アプリの開発を依頼した人達はコンピュータとしてのパソコンの有用性を理解していたが、開発当初はまだ「パソコン = ゲームマシン」の意識の人が多かった。「パソコンやっているならこれ手伝ってくりない ?」とか「好きなパソコンやって給料もらえるなんていいね」などと言われもした。しかし、本職以外である業務アプリの開発は壮絶だった。
自宅残業、自宅休日出勤の連続で寝不足の毎日が続いた。それでも「便利で助かっている」と言われと嬉しかった。ある朝、フラフラの状態で出勤して事務所に行くとある中年の女子職員が「課長 ! マコちゃんをあまりイジメないで !」と言った。苦笑いを返したその人こそ業務アプリの開発を依頼した張本人である。その課長は時々、わずかではあるが残業手当を支給するように手配してくれた。これも少しは嬉しかった。
誠のような立場の人は「職場プログラマ」と呼ばれていた。ネットには、そのような人が集まる掲示板があった。そこでお互いの傷を舐めあったのである。今から考えると彼らは PTSD (心的外傷後ストレス障害) の人達だったと言えるだろう。
誠は山が好きだった。若いころはよく山に行った。業務アプリの開発を始めてからは山から遠ざかっていくようになった。開発の重圧から解放されてからは、再び少しずつ一人で山に行くようになっていった。ロッククライミングなどの激しいことはやらなくなったが、昔はほとんど行くことがなかった東京近郊の山々に出かけるようになった。
急坂の登山道を喘ぎながら登っていると、頭の中で「少し休んでいかないかい ?」と言う声が聞こえたような気がした。辺りを見回すと、登山道から少し離れた草むらに座っている老人が微笑みながら「少し休んでいかないかい ?」と語りかけてきた。今度はハッキリ聞こえた。急ぐ旅ではなかったので老人の隣座り、水を一口飲んで喉を潤した。いろいろな四方山話をしていると名前を訊かれたので「次村 誠と言います」と答えて。「じゃぁ、マコさんだな。マコさんと呼ぶことにする」と言う。老人は「私のことは『じいさん』とでも呼んでくれ」と言うのでそうすることにした。休憩の後、二人で頂上まで登った。
下山の途中、また会えないかと言うので山と日にちとおおよその時刻を決めて逢うことにした。そんなことを繰り返して一緒に山登りをしているある時、じいさんが
「お前さん、空を飛んでみたいと思わないかい ?」
と訊いてきた。
「空をですか ? そうですねぇ、確かに鳥のように空を飛べたらいいとは思いますけど、でも、飛べない方がいいでしょう。きっと」
「何故だい ?」
「人間つていうのは自分達と異質のものは排除しようとしますからねぇ。魔女狩りなんてのもありまし、今でも同じようようなことが起こっていると思うんです。みにくいアヒルの子もそうですよね。みにくいアヒルの子は育ての親のおかげて死ぬことはなかったですけど。空を飛べるだけでも強力な攻撃になるのに、アニメのドラゴンボール Z の主人公のような人達が近くにいたら恐怖ですよ。かっとなって気功波をぶっ放されたら一瞬でお陀仏です。そう言えば、子供の頃、飛んでいる鳥に石を投げて落とそうとしたことがあります。何回も。でも空を飛べれば災害の時の救助に役に立つかも知れないな。でも、その後、石投げられて落とされたりして・・・」
「ハハハッ、マコさん、お前さん面白いこと言うねぇ。よし、分かった。わしが飛び方を教えてあげよう ! 騙されたつもりで修業しないか ? 空を飛べるようになったとしても人前で飛ばなきゃいい」
別に面白いことを言ったつもりはないが、誠は「う~ん」と唸ってしばらく考えて、いや、実は唸っただけで何も考えなかったのであるが、じいさんの話しに乗ることにした。
昔、誠はほんのわずかの間ではあるが空手を習ってしたことがある。その道場では夏と冬に合宿があった。その合宿で不思議な体験をした。二人が向かい合って立ち、相手を抱き上げるように垂直に持ち上げる。体重にかなりの違いがない限り相手を持ち上げることができる。次に、持ち上げられる方が「自分は絶対に持ち上がらない」と強く念じるのである。そうすると持ち上がらなくなる。持ち上げられる方の意識が働くのか、持ち上げる方が暗示にかかるのは分からない。VR (バーチャル・リアリティ:仮想現実) でマッチョな人がバーベルを持ち上げる映像みてバーベールを持ち上げると、いつもより重いバーベルを持ち上げることができるという実験がある。テレビの光の回折関係の科学番組で、観察者が念じると光が曲がるという実験結果もあった。
物理学者ファインマンの著書にこんな記述がある。「我々は天体の動きも原子の動きも計算できるが、原子の集まりである人の心や意識、精神については計算できない。もしかしたら霊や魂が人の本質かも知れない。しかし我々はそれを説明できないし証明もできな」 それらの現象の一部は脳科学で説明できるらしいが、その説明の現象が何故起こるのかということは説明できない。つまり、現象の法則性は説明できても「本当の意味の何故 ?」は説明できない。
人間の能力には計り知れないものがある。スポーツ選手の競技を見ていると本当にそう思う。人は、訓練し努力して鍛えると、とんでもない能力を身に付ける可能性がある。フリークライミングというのがある。ほとんど掴むような出っ張りがない岸壁を登るのだ。庇のように飛び出したオーバーハングを登っていく若い人を見て「あれはトリックだ !」と言った山の先輩がいた。空手で鍛えた人の破壊力も凄まじい。
物理的に人間が空を飛べるとは思っていなかったが、そんな、人の心や精神、能力の不思議さ を感じて興味があったことから、じいさんの話に乗ることにしたのだ。
じいさんが指定した民宿に着いたのは、まだ日が明るい夕方だった。その民宿は、伊豆の下田の先の駅から歩いて 40 分程のところにあった。最近は地域活性化とかで豪華なホテルや旅館が建設されているようだが、この民宿は昔ながらの民宿だ。この方が気持ちが落ち着くし宿泊料金も安い。民宿からは海が見え、小さい浜辺がある。夏は地元の人達が海水浴に来るが、観光客はほとんど来ない静かな浜辺だそうだ。まず、じいさんは
「さて、いよいよ始まるが、最初に言っておく。途中でやめたくなったらいつでやめる。お前さん次第だ」
と言った。「はい」と答えた。
じいさんと浜辺に出て、初日は夕方だけたが 3 泊 4 日の合宿が始まった。
海に向かって立ち、手の平を広げて肘を曲げ何かを抱えるようにして目を閉じる。海からやって来る風がここちよく感じる。その状態で 15 から 20 分間程何も考えないようにする。つまり、瞑想だ。これを「気を取り込む」と言う。これは空手の合宿でも教わった。海や山では気を感じやすいと言っていた。始めた頃はこの時間が長く感じで腕も疲れてくる。繰り返す内に時間を感じなくなってきた。翌朝は起床したら 8 Km 程のランニングをしてから朝食。休憩して柔軟体操、腕立て伏せ、腹筋、スクワットなどの筋トレの後に気を取り込む訓練してから昼飯。休憩したら筋トレしてから気を取り込む訓練。休憩して夕方にまたきを取り込む訓練。この繰り返しだ。
4ヶ月目に入った合宿の最後にじいさんから指示があった。
今度はは 2 週間後だな。家で訓練していると思うが、次回まで気を取り込む訓練は禁止だ。師匠の指示に従うのも訓練の内だからな。ハハハッ」
家では朝と夜に気を取り込む訓練をしていた。昼は職場の屋上でやっていたが、じぃさんの言い付けに従って中止した。筋トレとランニングはそのまま続けた。
その 2週間後の合宿は、じいさんの「うん、言い付けは守ったようだな。いいだろう」の言葉で始まった。2日目の昼前の気を溜める訓練の時だった。突然、海の波の音が消えた。聞こえなくなった。海の匂いもしなくなった。風を感じなくなった。その瞬間、下腹部に何かが勢いよくぶつかってきた。空中でじいさんに後ろから抱き抱えられてゆっくり地上に着いた。何が起きたのか分からなかった。一瞬気を失ってしまったようだ。心臓がバクバクして、ハァハァと激しい息切れがした。
「静かに息を吸うんだ。ゆっりくだ・・・。今度はゆっくり吐いて・・・。もう一度・・・、もう一度、息吹だ」
掌を上に向けて両手を前に出し、徐々に拳を握りしめて徐々に力を入れて腕を手前に引き寄せて息を腹に溜めていく。今度は、徐々に掌を広がながら徐々に両手を前に出していき、腹に溜め息をゆっくり最後まで吐き出す。これが息吹だ。登山で急な登りが長く続いた後、息吹を 3 回もやると息切れが収まる。これも空手で教わった。
「さぁ、昼飯だ !」と言うじいさんの後に付いて民宿に戻った。昼食はいつも山菜うどんとおにぎりである。それに漬物とトッピングとして玉子か揚げ物が付く。食事が終わった後、お茶を飲みながらじいさんが話出した。
「まこさん、お前さんさっき空を飛んだんだよ。いや、飛んだというよりは飛ばされたんだな。あれが気だ。空を自由に飛ぶには、この気をコントロール出来なきゃならい。午後からは気のコントロールの訓練だ。もし家で訓練していたら、飛ばされて、頭を柱なんかにぶつけて死んでしまったかもしれんな。ワッハハッ。まぁ、そういうことだ」
気をコントロールする訓練が始まった。周りの音が消える、静かになる瞬間、意識的に気を抑える。周りの音が聞こえ始める。
「そのまま、そのまま。ゆっくり静か~に今感じるやつを胸の方に押していくんだ。ゆっくりだ」
じいさんの指示が続く。
「ようしその調子だ。それを上、頭の方と、下、足の方にいくようにしずかに押していく。そうだ。その調子だ。いいぞ、いいぞ。今度は意識を持ってそれを横方向に広げる。気が体の後ろに回っていく。ゆっくり静かにだ。そ~っとだ」
体全体が妙な感触がしている。
いい感じになっている。そのままで眼をそっと開けてみろ」
眼をそっと開けると体全体に薄いもやかかった感じになっている。前に立っているじいさんの体ももやっとしている。 「もやっとしているだろう ? これは本当にもやっとしているんではないんだ。気を感じるとこう見える。しばらくすると見えなくなるが、気は感じる。意識すればもやっと見える。そのままで腕を下に下げてしって気の状態をそままま保ったままにする」
もやっとしたものが徐々に消えていったが、眼を瞑っていた時の感触はそのままだった。
「ここまでは飛ばされないようにゆっくりやったが、眼を開けたままで今の状態に徐々に速くしいくんだ。最後は瞬間的に今の状態になるまで練習する。いいな」
この訓練は夕食前まで続けられた。
今回の合宿の最終日は、朝食を済ませて帰る準備をしてから民宿の右手の裏にある山に登った。30分も登ると平坦な草むらがあった。その向こうには植林の森が続ていいる。じいさんと向かい合って立ち、両腕を広げて体全体に気を取り込んだ。「少し難しいかも知れんが、体、肉体の体ではなく気全体を上に移動するんだ。ゆっくり、静か~に」の指示でやってみた。足が地面、地上から徐々に離れていった。1 m ぐらいまで上昇した。「今度は下へ、下だ」で地上に降りて来た。浮いた !! 空、いや宙に浮いた~ !! 今度は 50 cm ぐらい浮いたところで正座しろと言う。正座 ? あれっ ? 正座できない。じいさんを見ると正座している。
「できないだろう ? 宙に浮いているということは無重力状態と同じなんだ。無重力状態ば正座はできない。星座した状態にするには気を部分的にコントロールする必要があるんた。これは自分で考えて体、体感で覚えるしかない。頑張れよ」
少し時間がかかったが空中で正座ができるようになった。何となく部分的な気のコントロールの方法か分かった気がした。
地上から 3 m 程の高さで上を向いて横になる。体軸を中心にして右回りに回転、左回りに回転。腕を体から離して右回り、左回り。つま先を中心にして回転、逆方向に回転。頭を中心にして回転、逆方向に回転。今度は膝と腰を曲げて丹田、臍の辺りを中心にして回転、逆方向に回転する。これを繰り返し練習した。眼が回ってきた。
じいさんが 1 m ぐらいまで下がれと言う。下がると、じいさんは誠の両肩を持って誠の体を思いきり回転させた。うぁ~、、あ~と叫んで四つん這いで地面に落下した。めまいがする。地面が揺れている。吐いた。
「この訓練は必要だ。飛んでいる時、急激に方向を変えると頭が急激に動く。すると脳みそが頭蓋骨の中で揺れて損傷したり三半規管もおかしく成る。それに対応するためだ。ボクシングの選手なども頭部へのパンチに備えて同じような訓練をするわけだ。脳みそだけじゃぁない。筋肉だっていきなり強い負荷を与えれば損傷する。少しずつ負荷を増やしていけば強い負荷にも耐えるにようになるわけだよ。勉強だって同じさ。少しずつ勉強していけば学習能力が高まっていく。語学の学習なんかいい例だな。もっとも、人間がいくら訓練してもキツツキのような激しい動作に耐える脳みそにはなれんかも知れんがな。ハッハハハ」
そう言えば、空手の練習でも同じようなのがあった。互いに向き合った相手の頭を両手で抑えて動かすのだ。ラジオ体操の首の運動は、空手の練習では勢いよく左右に向けたり、勢いよく回したりする。
じいさんは静かに微笑みながら話した。
「正直言って、お前さんがこれほど早くここまで来るとは思わなかったよ。半年、もしかしたら 2 年以上かかると思っていたんだ。わしの言うことを素直に真に受けて従ってくれたかも知れんな。ありがとうよ。でも、そういう人間は、詐欺にかかりやすいかも知れんぞ。注意してくれよ」
どうやら、空の飛び方を教えてやると言っても、乗ってくる人はほとんどいないと言う。そりゃそうだろう。このじいさん頭がおかしいじゃねぇか、と思われるのおちだろう。
じいさんと向かい合って宙に浮いた。じいさんの動きに合わせて動く訓練だ。じいさんが右に移動したらその方向に移動する。移動の速さも同期させる。右に左に。前に後ろに、斜めに。上に下に、やがてじいさんが樹林帯の中に移動していった。段々と速く、段々と体を水平にしながら。
「ついて来い !!」
と叫んだじいさんのスピードは益々上がった。右に曲がり、左に曲がり、樹林帯の林の斜面を上がって行く。スピードを上げると通過した樹林の木が激しく揺れ動く。上に向かって樹林の遥か上に、空中に出た。今度は頭から樹林帯に突っ込んで行く。再び空中に登って行く。今度は足から樹林の中に入って行った。樹林の中を下って元の草地に着いた。
「さぁ~てと、今回の合宿はこれで終わりだ。次回は場所を変えるぞ」
1 週間ほど休めるかと訊かれたので、2 週間後には正月休みなので有給休暇を使えば 10 日ほど休めると答えだ。じいさんは、それで十分だと言った。
空を飛んだ。空を飛べた。4 ヶ月程前に「空なんて飛べなくていいですよ」と言ったが、飛んでみるといい気持ちだった。感激して興奮した。ここ伊豆での合宿は、小雨の時もあったが天気には恵まれた。駅に向かって歩きながら、民宿と浜辺の方を何度も何度も振り返った。
じいさんは言った。
次村 誠 (ツギムラ マコト) は 50 歳を過ぎていた。勤務先の施設内にある診療所の診療放射線技師だ。本来の仕事の他にも、パソコンに詳しいと言う理由で、新たに赴任してきた課長と、転職してきた数人の事務職の人達に頼まれて、パソコンで使用する業務関係のアプリの開発も行っていた。
当時、職場にはパソコンは一台もなかった。新たに赴任してきた課長が導入を決めたのである、誠はパソコン購入の担当にさせられた。
誠が務める機関では年間を通じて、パート職員の手を借りる多くの行事が催されている。正規職員の給与関係の処理はホストコンピュータによって行われていたが、パート職員の賃金の処理は、事務の人が電卓と集計表という用紙を使用して手作業で処理されていた。
開発したアプリの効果は絶大だった。毎日の処理は不要になり、月末に勤務表の内容を入力するだけになった。この作業は 1 時間程で十分だった。手書きで 4 日間もかかった年末の源泉徴収票の作成は、プリンタが自動で印刷するようになった。30 分も待てば印刷は終了する。
このことが契機になつて、官公庁関係への報告書や診療関係の業務アプリの開発の依頼が増えていった。
部署内にパソコンが増えてくると「LAN を組むと便利だ」と言う者が現れた。余計なことを言うやつだ。結局、部署内サーバを置くことになり誠が担当者にされて、予算が足りないということで LAN 工事も行った。インターネットを利用する提案もあったが、誠は反対した。当時はインターネット接続の電話料金は従量制だった。業務アプリの開発ほとんど自宅でやっていたが、開発、つまりプログラミング関係の情報はインターネットで得ていた。接続時間が長い月には、電話会社から確認の電話を受けたことが何回もあったのだ。もし職場でインターネット接続するとなると、相当の出費となる可能性があると思ったからである。
やがて IT 化の波が押し寄せてきた。情報管理部門が設置され、組織全体のサーバが設置されたが、実際の管理は外部委託となった。パソコンの OS と機種が統一されクラウド化されていった。個人が作成したプログラム類の使用は禁止され、これまで開発した業務アプリは使用できなくなったのである。業務アプリで処理していた作業は表計算ソフトや文書作成ソフトで行うことになったが、それらのソフトによる処理は、手作業で行っていた時よりも時間がかかるようになった。まずは、それらのソフトの使用方法にどを習得しなければないらい。開発という重圧から解放されたが、今度は、それらのソフトの使用方法などを教える立場になってしまった。
業務アプリの開発を依頼した人達はコンピュータとしてのパソコンの有用性を理解していたが、開発当初はまだ「パソコン = ゲームマシン」の意識の人が多かった。「パソコンやっているならこれ手伝ってくりない ?」とか「好きなパソコンやって給料もらえるなんていいね」などと言われもした。しかし、本職以外である業務アプリの開発は壮絶だった。
自宅残業、自宅休日出勤の連続で寝不足の毎日が続いた。それでも「便利で助かっている」と言われと嬉しかった。ある朝、フラフラの状態で出勤して事務所に行くとある中年の女子職員が「課長 ! マコちゃんをあまりイジメないで !」と言った。苦笑いを返したその人こそ業務アプリの開発を依頼した張本人である。その課長は時々、わずかではあるが残業手当を支給するように手配してくれた。これも少しは嬉しかった。
誠のような立場の人は「職場プログラマ」と呼ばれていた。ネットには、そのような人が集まる掲示板があった。そこでお互いの傷を舐めあったのである。今から考えると彼らは PTSD (心的外傷後ストレス障害) の人達だったと言えるだろう。
誠は山が好きだった。若いころはよく山に行った。業務アプリの開発を始めてからは山から遠ざかっていくようになった。開発の重圧から解放されてからは、再び少しずつ一人で山に行くようになっていった。ロッククライミングなどの激しいことはやらなくなったが、昔はほとんど行くことがなかった東京近郊の山々に出かけるようになった。
急坂の登山道を喘ぎながら登っていると、頭の中で「少し休んでいかないかい ?」と言う声が聞こえたような気がした。辺りを見回すと、登山道から少し離れた草むらに座っている老人が微笑みながら「少し休んでいかないかい ?」と語りかけてきた。今度はハッキリ聞こえた。急ぐ旅ではなかったので老人の隣座り、水を一口飲んで喉を潤した。いろいろな四方山話をしていると名前を訊かれたので「次村 誠と言います」と答えて。「じゃぁ、マコさんだな。マコさんと呼ぶことにする」と言う。老人は「私のことは『じいさん』とでも呼んでくれ」と言うのでそうすることにした。休憩の後、二人で頂上まで登った。
下山の途中、また会えないかと言うので山と日にちとおおよその時刻を決めて逢うことにした。そんなことを繰り返して一緒に山登りをしているある時、じいさんが
「お前さん、空を飛んでみたいと思わないかい ?」
と訊いてきた。
「空をですか ? そうですねぇ、確かに鳥のように空を飛べたらいいとは思いますけど、でも、飛べない方がいいでしょう。きっと」
「何故だい ?」
「人間つていうのは自分達と異質のものは排除しようとしますからねぇ。魔女狩りなんてのもありまし、今でも同じようようなことが起こっていると思うんです。みにくいアヒルの子もそうですよね。みにくいアヒルの子は育ての親のおかげて死ぬことはなかったですけど。空を飛べるだけでも強力な攻撃になるのに、アニメのドラゴンボール Z の主人公のような人達が近くにいたら恐怖ですよ。かっとなって気功波をぶっ放されたら一瞬でお陀仏です。そう言えば、子供の頃、飛んでいる鳥に石を投げて落とそうとしたことがあります。何回も。でも空を飛べれば災害の時の救助に役に立つかも知れないな。でも、その後、石投げられて落とされたりして・・・」
「ハハハッ、マコさん、お前さん面白いこと言うねぇ。よし、分かった。わしが飛び方を教えてあげよう ! 騙されたつもりで修業しないか ? 空を飛べるようになったとしても人前で飛ばなきゃいい」
別に面白いことを言ったつもりはないが、誠は「う~ん」と唸ってしばらく考えて、いや、実は唸っただけで何も考えなかったのであるが、じいさんの話しに乗ることにした。
昔、誠はほんのわずかの間ではあるが空手を習ってしたことがある。その道場では夏と冬に合宿があった。その合宿で不思議な体験をした。二人が向かい合って立ち、相手を抱き上げるように垂直に持ち上げる。体重にかなりの違いがない限り相手を持ち上げることができる。次に、持ち上げられる方が「自分は絶対に持ち上がらない」と強く念じるのである。そうすると持ち上がらなくなる。持ち上げられる方の意識が働くのか、持ち上げる方が暗示にかかるのは分からない。VR (バーチャル・リアリティ:仮想現実) でマッチョな人がバーベルを持ち上げる映像みてバーベールを持ち上げると、いつもより重いバーベルを持ち上げることができるという実験がある。テレビの光の回折関係の科学番組で、観察者が念じると光が曲がるという実験結果もあった。
物理学者ファインマンの著書にこんな記述がある。「我々は天体の動きも原子の動きも計算できるが、原子の集まりである人の心や意識、精神については計算できない。もしかしたら霊や魂が人の本質かも知れない。しかし我々はそれを説明できないし証明もできな」 それらの現象の一部は脳科学で説明できるらしいが、その説明の現象が何故起こるのかということは説明できない。つまり、現象の法則性は説明できても「本当の意味の何故 ?」は説明できない。
人間の能力には計り知れないものがある。スポーツ選手の競技を見ていると本当にそう思う。人は、訓練し努力して鍛えると、とんでもない能力を身に付ける可能性がある。フリークライミングというのがある。ほとんど掴むような出っ張りがない岸壁を登るのだ。庇のように飛び出したオーバーハングを登っていく若い人を見て「あれはトリックだ !」と言った山の先輩がいた。空手で鍛えた人の破壊力も凄まじい。
物理的に人間が空を飛べるとは思っていなかったが、そんな、人の心や精神、能力の不思議さ を感じて興味があったことから、じいさんの話に乗ることにしたのだ。
じいさんが指定した民宿に着いたのは、まだ日が明るい夕方だった。その民宿は、伊豆の下田の先の駅から歩いて 40 分程のところにあった。最近は地域活性化とかで豪華なホテルや旅館が建設されているようだが、この民宿は昔ながらの民宿だ。この方が気持ちが落ち着くし宿泊料金も安い。民宿からは海が見え、小さい浜辺がある。夏は地元の人達が海水浴に来るが、観光客はほとんど来ない静かな浜辺だそうだ。まず、じいさんは
「さて、いよいよ始まるが、最初に言っておく。途中でやめたくなったらいつでやめる。お前さん次第だ」
と言った。「はい」と答えた。
じいさんと浜辺に出て、初日は夕方だけたが 3 泊 4 日の合宿が始まった。
海に向かって立ち、手の平を広げて肘を曲げ何かを抱えるようにして目を閉じる。海からやって来る風がここちよく感じる。その状態で 15 から 20 分間程何も考えないようにする。つまり、瞑想だ。これを「気を取り込む」と言う。これは空手の合宿でも教わった。海や山では気を感じやすいと言っていた。始めた頃はこの時間が長く感じで腕も疲れてくる。繰り返す内に時間を感じなくなってきた。翌朝は起床したら 8 Km 程のランニングをしてから朝食。休憩して柔軟体操、腕立て伏せ、腹筋、スクワットなどの筋トレの後に気を取り込む訓練してから昼飯。休憩したら筋トレしてから気を取り込む訓練。休憩して夕方にまたきを取り込む訓練。この繰り返しだ。
4ヶ月目に入った合宿の最後にじいさんから指示があった。
今度はは 2 週間後だな。家で訓練していると思うが、次回まで気を取り込む訓練は禁止だ。師匠の指示に従うのも訓練の内だからな。ハハハッ」
家では朝と夜に気を取り込む訓練をしていた。昼は職場の屋上でやっていたが、じぃさんの言い付けに従って中止した。筋トレとランニングはそのまま続けた。
その 2週間後の合宿は、じいさんの「うん、言い付けは守ったようだな。いいだろう」の言葉で始まった。2日目の昼前の気を溜める訓練の時だった。突然、海の波の音が消えた。聞こえなくなった。海の匂いもしなくなった。風を感じなくなった。その瞬間、下腹部に何かが勢いよくぶつかってきた。空中でじいさんに後ろから抱き抱えられてゆっくり地上に着いた。何が起きたのか分からなかった。一瞬気を失ってしまったようだ。心臓がバクバクして、ハァハァと激しい息切れがした。
「静かに息を吸うんだ。ゆっりくだ・・・。今度はゆっくり吐いて・・・。もう一度・・・、もう一度、息吹だ」
掌を上に向けて両手を前に出し、徐々に拳を握りしめて徐々に力を入れて腕を手前に引き寄せて息を腹に溜めていく。今度は、徐々に掌を広がながら徐々に両手を前に出していき、腹に溜め息をゆっくり最後まで吐き出す。これが息吹だ。登山で急な登りが長く続いた後、息吹を 3 回もやると息切れが収まる。これも空手で教わった。
「さぁ、昼飯だ !」と言うじいさんの後に付いて民宿に戻った。昼食はいつも山菜うどんとおにぎりである。それに漬物とトッピングとして玉子か揚げ物が付く。食事が終わった後、お茶を飲みながらじいさんが話出した。
「まこさん、お前さんさっき空を飛んだんだよ。いや、飛んだというよりは飛ばされたんだな。あれが気だ。空を自由に飛ぶには、この気をコントロール出来なきゃならい。午後からは気のコントロールの訓練だ。もし家で訓練していたら、飛ばされて、頭を柱なんかにぶつけて死んでしまったかもしれんな。ワッハハッ。まぁ、そういうことだ」
気をコントロールする訓練が始まった。周りの音が消える、静かになる瞬間、意識的に気を抑える。周りの音が聞こえ始める。
「そのまま、そのまま。ゆっくり静か~に今感じるやつを胸の方に押していくんだ。ゆっくりだ」
じいさんの指示が続く。
「ようしその調子だ。それを上、頭の方と、下、足の方にいくようにしずかに押していく。そうだ。その調子だ。いいぞ、いいぞ。今度は意識を持ってそれを横方向に広げる。気が体の後ろに回っていく。ゆっくり静かにだ。そ~っとだ」
体全体が妙な感触がしている。
いい感じになっている。そのままで眼をそっと開けてみろ」
眼をそっと開けると体全体に薄いもやかかった感じになっている。前に立っているじいさんの体ももやっとしている。 「もやっとしているだろう ? これは本当にもやっとしているんではないんだ。気を感じるとこう見える。しばらくすると見えなくなるが、気は感じる。意識すればもやっと見える。そのままで腕を下に下げてしって気の状態をそままま保ったままにする」
もやっとしたものが徐々に消えていったが、眼を瞑っていた時の感触はそのままだった。
「ここまでは飛ばされないようにゆっくりやったが、眼を開けたままで今の状態に徐々に速くしいくんだ。最後は瞬間的に今の状態になるまで練習する。いいな」
この訓練は夕食前まで続けられた。
今回の合宿の最終日は、朝食を済ませて帰る準備をしてから民宿の右手の裏にある山に登った。30分も登ると平坦な草むらがあった。その向こうには植林の森が続ていいる。じいさんと向かい合って立ち、両腕を広げて体全体に気を取り込んだ。「少し難しいかも知れんが、体、肉体の体ではなく気全体を上に移動するんだ。ゆっくり、静か~に」の指示でやってみた。足が地面、地上から徐々に離れていった。1 m ぐらいまで上昇した。「今度は下へ、下だ」で地上に降りて来た。浮いた !! 空、いや宙に浮いた~ !! 今度は 50 cm ぐらい浮いたところで正座しろと言う。正座 ? あれっ ? 正座できない。じいさんを見ると正座している。
「できないだろう ? 宙に浮いているということは無重力状態と同じなんだ。無重力状態ば正座はできない。星座した状態にするには気を部分的にコントロールする必要があるんた。これは自分で考えて体、体感で覚えるしかない。頑張れよ」
少し時間がかかったが空中で正座ができるようになった。何となく部分的な気のコントロールの方法か分かった気がした。
地上から 3 m 程の高さで上を向いて横になる。体軸を中心にして右回りに回転、左回りに回転。腕を体から離して右回り、左回り。つま先を中心にして回転、逆方向に回転。頭を中心にして回転、逆方向に回転。今度は膝と腰を曲げて丹田、臍の辺りを中心にして回転、逆方向に回転する。これを繰り返し練習した。眼が回ってきた。
じいさんが 1 m ぐらいまで下がれと言う。下がると、じいさんは誠の両肩を持って誠の体を思いきり回転させた。うぁ~、、あ~と叫んで四つん這いで地面に落下した。めまいがする。地面が揺れている。吐いた。
「この訓練は必要だ。飛んでいる時、急激に方向を変えると頭が急激に動く。すると脳みそが頭蓋骨の中で揺れて損傷したり三半規管もおかしく成る。それに対応するためだ。ボクシングの選手なども頭部へのパンチに備えて同じような訓練をするわけだ。脳みそだけじゃぁない。筋肉だっていきなり強い負荷を与えれば損傷する。少しずつ負荷を増やしていけば強い負荷にも耐えるにようになるわけだよ。勉強だって同じさ。少しずつ勉強していけば学習能力が高まっていく。語学の学習なんかいい例だな。もっとも、人間がいくら訓練してもキツツキのような激しい動作に耐える脳みそにはなれんかも知れんがな。ハッハハハ」
そう言えば、空手の練習でも同じようなのがあった。互いに向き合った相手の頭を両手で抑えて動かすのだ。ラジオ体操の首の運動は、空手の練習では勢いよく左右に向けたり、勢いよく回したりする。
じいさんは静かに微笑みながら話した。
「正直言って、お前さんがこれほど早くここまで来るとは思わなかったよ。半年、もしかしたら 2 年以上かかると思っていたんだ。わしの言うことを素直に真に受けて従ってくれたかも知れんな。ありがとうよ。でも、そういう人間は、詐欺にかかりやすいかも知れんぞ。注意してくれよ」
どうやら、空の飛び方を教えてやると言っても、乗ってくる人はほとんどいないと言う。そりゃそうだろう。このじいさん頭がおかしいじゃねぇか、と思われるのおちだろう。
じいさんと向かい合って宙に浮いた。じいさんの動きに合わせて動く訓練だ。じいさんが右に移動したらその方向に移動する。移動の速さも同期させる。右に左に。前に後ろに、斜めに。上に下に、やがてじいさんが樹林帯の中に移動していった。段々と速く、段々と体を水平にしながら。
「ついて来い !!」
と叫んだじいさんのスピードは益々上がった。右に曲がり、左に曲がり、樹林帯の林の斜面を上がって行く。スピードを上げると通過した樹林の木が激しく揺れ動く。上に向かって樹林の遥か上に、空中に出た。今度は頭から樹林帯に突っ込んで行く。再び空中に登って行く。今度は足から樹林の中に入って行った。樹林の中を下って元の草地に着いた。
「さぁ~てと、今回の合宿はこれで終わりだ。次回は場所を変えるぞ」
1 週間ほど休めるかと訊かれたので、2 週間後には正月休みなので有給休暇を使えば 10 日ほど休めると答えだ。じいさんは、それで十分だと言った。
空を飛んだ。空を飛べた。4 ヶ月程前に「空なんて飛べなくていいですよ」と言ったが、飛んでみるといい気持ちだった。感激して興奮した。ここ伊豆での合宿は、小雨の時もあったが天気には恵まれた。駅に向かって歩きながら、民宿と浜辺の方を何度も何度も振り返った。
Copyright @ Izu Daiwaka