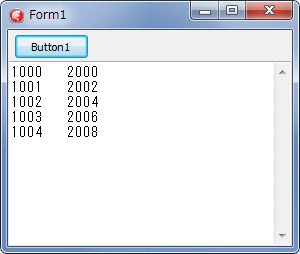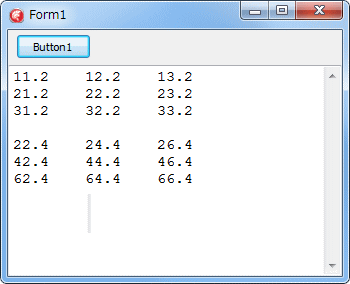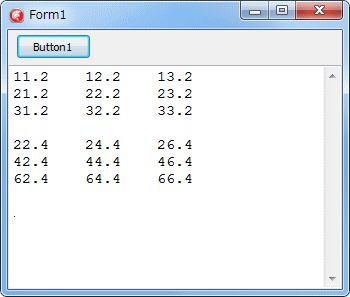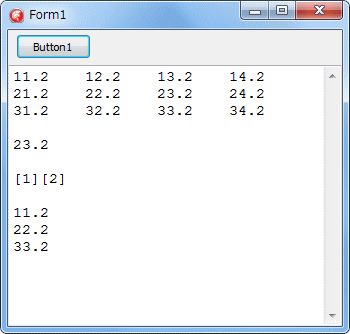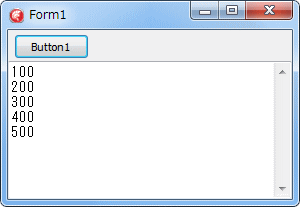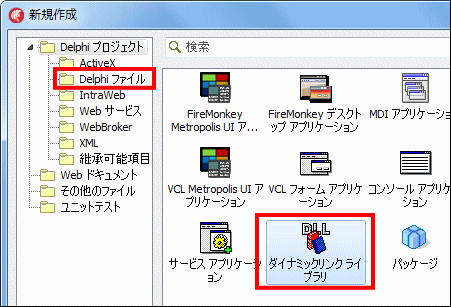Delphi Programming / Object Pascal Delphi 一般・その他
Windows API 等、DLL の関数の配列型引数
動作確認等
Windows 7 U64(SP1) + Delphi XE5(UP2) Pro VCL-32
Windows API 等、DLL 内の関数の配列型引数
数値型の配列の引数が、ポインタ型である DLL 内の配列処理用の関数を使用する時、あるいは、DLL に組み込む汎用的な配列処理用の関数を Delphi で作成する際の参考記事です。
次のような引数の定義の関数があったとします。 これは、引数が整数型と実数型の要素を持つ 1 次元の配列で、要素数が固定の配列を意味しています。
BOOL test_conv(
int src[10],
float dst1[5],
float dst2[5]
);
要素数が固定でなければ以下の定義と同じです。つまり、ポインタ型です。
BOOL test_conv(
int *src,
float *dst1,
float *dst2
);
この関数は Delphi には実装されていないのですから、Delphi には実装されていないWindows API の関数を利用とする時と同じように、使用する関数を宣言します。
// 汎用的なポインタ型で定義function test_conv(src: Pointer; dst1: Pointer; dst2: Pointer): Boolean;stdcall ; external 'dll_testarray.dll' ;
配列の変数は例えば以下のようにします。型を定義して使用することもできます。
// 1 次元の静的配列を使用する場合var Lsrc_dat : array [0 ..9 ] of Integer;
Ldst1_dat : array [0 ..4 ] of Single;
Ldst2_dat : array [0 ..4 ] of Single;
// 1 次元の動的配列を使用する場合var Lsrc_dat : array of Integer;
Ldst1_dat : array of Single;
Ldst2_dat : array of Single;
// 動的配列は実行時に要素の設定が必要SetLength(Lsrc_dat, 10 );
SetLength(Ldst1_dat, 5 );
SetLength(Ldst2_dat, 5 );
// 関数を実行// 配列の最初の要素のアドレスを渡すtest_conv(@Lsrc_dat[0 ], @Ldst1_dat[0 ], @Ldst2_dat[0 ]);
[備考 1]
[備考 2]
1 次元の静的配列を処理する関数とその関数を使用する例です。
// 以下のどちらでも構わないtest_conv(5 , @Lsrc_dat, @Ldst_dat);
test_conv(5 , @Lsrc_dat[0 ], @Ldst_dat[0 ]);
本ページのサンプルでは、引数のポインタ型として、汎用のポインタ型である Pointer
を使用していますが、以下のように、数値の型に応じたポインタ型を使用することもできます。実際、C や C++ の関数ではほとんどそうなっています。
function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:PSingle): Boolean;
図1
リスト1
copy code
unit Unit1;interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// 1 次元配列の引数をポインタで渡す例// 静的配列の場合// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var Lsrc_dat : array [0 ..4 ] of Single;
Ldst_dat : array [0 ..4 ] of Single;
LIndex : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.BeginUpdate;
for LIndex := Low(Lsrc_dat) to High(Lsrc_dat) do begin Lsrc_dat[LIndex]:=1000.0 + LIndex;
end ;// 関数を実行test_conv(5 , @Lsrc_dat[0], @Ldst_dat[0]);
// 関数の戻り値を表示for Lindex := Low(Ldst_dat) to High(Ldst_dat) do begin Memo1.Lines.Add(FloatToStr(Lsrc_dat[LIndex]) + ' '
+ FloatToStr(Ldst_dat[LIndex]));
end ;Memo1.Lines.EndUpdate;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を引数に持つ関数の例// 引数の配列が Single 型の静的配列と仮定した場合の処理例// // Windows API の関数や他の DLL 内の関数の実際の処理は不明// Windoows API の関数は DLL で提供されている// ----------------------------------------------------------------------------function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;var LpSrc : Single;
Lindex : Integer;
begin Result := True;
// 配列データを要素順に操作for Lindex := 0 to ASize - 1 do begin LpSrc := PSingle(ASrcArray)^;
PSingle(ADstArray)^ := LpSrc * 2.0 ;
// 次のデータのある場所 (ポインタ) に移動inc(PSingle(AsrcArray));
inc(PSingle(ADstArray));
end ;end ;end .
上のコードはポインタを連続的に移動して処理しているだけです
。配列に対して汎用的な処理を行うには、以下のように、任意の配列要素への代入や値の取得の機能が必要です。
リスト2
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// 指定要素の値を取得// 引数の ArrayPtr は配列の最初の要素のポインタ// ----------------------------------------------------------------------------function Get1DSingle(ArrayPtr: Pointer; AIndex: Integer): Single;begin // 配列の先頭要素からポインタをインクリメントinc(PSingle(ArrayPtr), AIndex);
// そのポインタにおける値を逆参照で取得Result := PSingle(ArrayPtr)^;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 指定要素に値を代入// ----------------------------------------------------------------------------procedure Set1DSingle(ArrayPtr: Pointer; AIndex: Integer; AValue: Single);begin inc(PSingle(ArrayPtr), AIndex);
PSingle(ArrayPtr)^ := AValue;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Single 型の静的配列// (2) 配列の最初の要素のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// ----------------------------------------------------------------------------function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;var LSrcValue : Single;
Lindex : Integer;
begin Result := True;
for Lindex := 0 to ASize - 1 do begin LSrcValue := Get1DSingle(ASrcArray, Lindex);
Set1DSingle(ADstArray, Lindex, LSrcValue * 2.0 );
end ;end ;
Delphi では配列を型定義して使用することができます。Delphi の型定義の静的配列を使用した関数の処理例です。
リスト3
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Single 型の静的配列// (2) 配列の最初の要素のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// ----------------------------------------------------------------------------function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;type TStatArray = array [0 ..$7FFFFFF ] of Single;
PStatArray = ^TStatArray;
var LpSrcArray : PStatArray;
LpDstArray : PStatArray;
Lindex : Integer;
begin Result := True;
// 最初の要素のポインタを取得LpSrcArray := PStatArray(ASrcArray);
LpDstArray := PStatArray(ADstArray);
for Lindex := 0 to ASize - 1 do begin LpDstArray^[Lindex] := LpSrcArray^[Lindex] * 2.0 ;
end ;end ;
1 次元の動的配列を処理する関数とその関数を使用する例です。
// 最初の配列要素のアドレスを渡すtest_conv(5 , @Lsrc_dat[0 ], @Ldst_dat[0 ]);
[備考]
関数の内部で、引数の配列を動的配列として処理している場合、その配列引数に静的配列を渡しても正常に処理できません。通常は例外が発生します。このことは、 1 次元の配列でも 2 次元の配列でも同じです。
下に示すコードは 1 次元の動的配列を処理する関数と使用例です。この場合は、以下のように配列自身のアドレスを引数に渡します。この関数では 1 次元の静的配列は処理できません。このような関数は 1 次元の動的配列専用の関数となります。
// 最初の配列要素のアドレスではなく、配列のアドレスを渡すtest_conv(5 , @Lsrc_dat, @Ldst_dat);
リスト4
copy code
unit Unit1;interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// 1 次元配列の引数をポインタで渡す例// 動的配列の場合// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var Lsrc_dat : array of Single;
Ldst_dat : array of Single;
LIndex : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.BeginUpdate;
SetLength(Lsrc_dat, 5 );
SetLength(Ldst_dat, 5 );
for LIndex := Low(Lsrc_dat) to High(Lsrc_dat) do begin Lsrc_dat[LIndex]:=1000.0 + LIndex;
end ;// 関数を実行test_conv(5 , @Lsrc_dat, @Ldst_dat);
// 関数の戻り値を表示for Lindex := Low(Ldst_dat) to High(Ldst_dat) do begin Memo1.Lines.Add(FloatToStr(Lsrc_dat[LIndex]) + ' '
+ FloatToStr(Ldst_dat[LIndex]));
end ;Memo1.Lines.EndUpdate;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を引数に持つ関数の例// 引数の配列が Single 型の動的配列と仮定した場合の処理例// // この関数の引数は、配列の先頭要素のアドレスではなく、配列のアドレスとする// // Windows API の関数や他の DLL 内の関数の実際の処理は不明// Windoows API の関数は DLL で提供されている// ----------------------------------------------------------------------------function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;var LSrcArrAdr : NativeUInt;
LDstArrAdr : NativeUInt;
LSrcData : Single;
Lindex : Integer;
begin Result := True;
// 配列のアドレスを取得// このアドレスは最初の配列要素のポインタLSrcArrAdr := PNativeUInt(ASrcArray)^;
LDstArrAdr := PNativeUInt(ADstArray)^;
// 配列データを要素順に操作for Lindex := 0 to ASize - 1 do begin LSrcData := PSingle(LSrcArrAdr)^;
PSingle(LDstArrAdr)^ := LSrcData * 2.0 ;
// 次のデータのある場所 (ポインタ) に移動inc(PSingle(LSrcArrAdr));
inc(PSingle(LDstArrAdr));
end ;end ;end .
上のコードはポインタを連続的に移動して処理しているだけです
。配列に対して汎用的な処理を行うには、以下のように、任意の配列要素への代入や値の取得の機能が必要です。
リスト5
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// 指定要素の値を取得// 引数の ArrayPtr は配列の最初の要素のアドレス// ----------------------------------------------------------------------------function GetDyn1DSingle(ArrayPtr: NativeUInt; AIndex: Integer): Single;begin // 配列の先頭要素からポインタをインクリメントinc(PSingle(ArrayPtr), AIndex);
// そのポインタにおける値を逆参照で取得Result := PSingle(ArrayPtr)^;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 指定要素に値を代入// ----------------------------------------------------------------------------procedure SetDyn1DSingle(ArrayPtr: NativeUInt; AIndex: Integer; AValue: Single);begin inc(PSingle(ArrayPtr), AIndex);
PSingle(ArrayPtr)^ := AValue;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Single 型の動的配列// (2) 配列のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// ----------------------------------------------------------------------------function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;var LpSrcArrAddr : NativeUInt;
LpDstArrAddr : NativeUInt;
LSrcData : Single;
Lindex : Integer;
begin Result := True;
// 配列のアドレスを取得// このアドレスは最初の配列要素のポインタLpSrcArrAddr := PNativeUInt(ASrcArray)^;
LpDstArrAddr := PNativeUInt(ADstArray)^;
for Lindex := 0 to ASize - 1 do begin LSrcData := GetDyn1DSingle(LpSrcArrAddr, Lindex);
SetDyn1DSingle(LpDstArrAddr, Lindex, LSrcData * 2.0 );
end ;end ;
Delphi では配列を型定義して使用することができます。Delphi の型定義の動的配列を使用すると、1 次元の動的配列の処理を以下のように書けます。
リスト6
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Single 型の動的配列// (2) 配列のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// ----------------------------------------------------------------------------function test_conv(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray:Pointer): Boolean;type TDynArray = array of Single;
PDynArray = ^TDynArray;
var LpSrcArray : PDynArray;
LpDstArray : PDynArray;
Lindex : Integer;
begin Result := True;
LpSrcArray := PDynArray(ASrcArray);
LpDstArray := PDynArray(ADstArray);
for Lindex := 0 to ASize - 1 do begin LpDstArray^[Lindex] := LpSrcArray^[Lindex] * 2.0 ;
end ;end ;
上のような処理コードであれば、以下のように、配列の要素数が取得てぎす。この値を利用すれば、関数の引数に配列の要素数がなくても処理できます。
LSize := LEngth(LpSrcArray^);
2 次元の静的配列を処理する関数とその関数を使用する例です。
引数には配列要素の最初のデータのアドレスを渡します。静的配列の配列自身のアドレスと、最初の要素のデータのアドレスは同じです。したがって、以下のどちらのでも処理できます。
2 次元の静的配列用として作成されている配列の処理は、2 次元の動的配列の処理はできません。
// 以下のどれでも構わない SetArrayElement(LSize, @LSrcArray, @LDstArray);
SetArrayElement(LSize, @LSrcArray[0 ], @LDstArray[0 ]);
SetArrayElement(LSize, @LSrcArray[0 ][0], @LDstArray[0 ][0]);
図2
リスト7
copy code
unit Unit1;interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
procedure FormCreate(Sender: TObject);procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// フォーム生成時の処理// =============================================================================procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);begin Memo1.Font.Charset := ANSI_CHARSET;
Memo1.Font.Name := 'Courier New' ;
Memo1.Font.Size := 11 ;
end ;// =============================================================================// 2 次元配列の引数をポインタで渡す例// 静的配列の場合// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LSrcArray : array [0 ..2 ] of array [0 ..2 ] of Double;
LDstArray : array [0 ..2 ] of array [0 ..2 ] of Double;
LSize : Integer;
LText : string ;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.BeginUpdate;
// 配列の各要素に値を代入for LRow := Low(LSrcArray) to High(LSrcArray) do begin for LCol := Low(LSrcArray[LRow]) to High(LSrcArray[LRow]) do begin LSrcArray[LRow, LCol] := (LRow + 1 ) * 10 + (LCol + 1 ) + 0.2 ;
end ;end ;// 代入した値を確認表示for LRow := Low(LSrcArray) to High(LSrcArray) do begin LText := '' ;
for LCol := Low(LSrcArray[LRow]) to High(LSrcArray[LRow]) do begin LText := LText + FormatFloat('0.0 ' , LSrcArray[LRow][LCol]);
end ;Memo1.Lines.Add(LText);
end ;// 関数の実行LSize := 3 ;
SetArrayElement(LSize, @LSrcArray[0 ][0 ], @LDstArray[0 ][0 ]);
// 関数の実行結果しての配列要素の値を表示Memo1.Lines.Add('' );
for LRow := Low(LDstArray) to High(LDstArray) do begin LText := '' ;
for LCol := Low(LDstArray[LRow]) to High(LDstArray[LRow]) do begin LText := LText + FormatFloat('0.0 ' , LDstArray[LRow][LCol]);
end ;Memo1.Lines.Add(LText);
end ;Memo1.Lines.EndUpdate;
end ;// -----------------------------------------------------------------------------// 2 次元配列を引数に持つ関数の例// 引数の配列が Double 型の2 次元の静的配列と仮定した場合の処理例// この関数は静的配列を渡さないと正常に処理できない// // Windows API の関数や他の DLL 内の関数の実際の処理は不明// Windoows API の関数は DLL で提供されている// -----------------------------------------------------------------------------function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;var LDstPtr : Pointer;
LSrcValue : Double;
LDstValue : Double;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Result := True;
// 引数のポインタの値を退避// 使用るす必要がなければ不要LDstPtr := Pointer(ADstArray);
for LRow := 0 to ASize - 1 do begin for LCol := 0 to ASize - 1 do begin // 配列要素の値を取得LSrcValue := PDouble(ASrcArray)^;
;
// 結果の配列要素に値を代入LDstValue := LSrcValue * 2.0 ;
PDouble(ADstArray)^ := LDstValue;
// 次のデータのある場所 (ポインタ) に移動inc(PDouble(ASrcArray));
inc(PDouble(ADstArray));
end ;end ;end ;end .
上のコードはポインタを連続的に移動して処理しているだけです
。配列に対して汎用的な処理を行うには、以下のように、任意の配列要素への代入や値の取得の機能が必要です。
リスト8
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// 指定要素の値を取得// 引数の ArrayPtr は配列の最初の要素のポインタ// 引数の ASize は配列の列数 // -----------------------------------------------------------------------------function Get2DDouble(ArrayPtr: Pointer; ASize, ARow, ACol: Integer): Double;begin // 配列の先頭からポインタをインクリメントinc(PDouble(ArrayPtr), ARow * ASize + ACol);
// そのポインタにおける値を逆参照で取得Result := PDouble(ArrayPtr)^;
end ;// -----------------------------------------------------------------------------// 指定要素に値を代入// -----------------------------------------------------------------------------procedure Set2DDouble(ArrayPtr: Pointer; ASize, ARow, ACol: Integer; AValue: Double);begin inc(PDouble(ArrayPtr), ARow * ASize + ACol);
PDouble(ArrayPtr)^ := AValue;
end ;// -----------------------------------------------------------------------------// 2 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Double 型の静的配列// (2) 配列の最初の要素のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// -----------------------------------------------------------------------------function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;var LSrcValue : Double;
LDstValue : Double;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Result := True;
for LRow := 0 to ASize - 1 do begin for LCol := 0 to ASize - 1 do begin LSrcValue := Get2DDouble(ASrcArray, ASize, LRow, LCol);
LDstValue := LSrcValue * 2.0 ;
Set2DDouble(ADstArray, ASize,LRow, LCol, LDstValue);
end ;end ;end ;
Delphi では配列を型定義して使用することができます。Delphi の型定義の静的配列を使用すると、2 次元の静的配列の処理を以下のように書けます。
リスト9
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// 2 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Double 型の静的配列// (2) 配列の最初の要素のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// -----------------------------------------------------------------------------function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;type TStatArray = array [0 ..$5FFFFFF ] of Double;
PStatArray = ^TStatArray;
var LpSrcArray : PStatArray;
LpDstArray : PStatArray;
LSrcValue : Double;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Result := True;
// 最初の要素のポインタを取得LpSrcArray := PStatArray(ASrcArray);
LpDstArray := PStatArray(ADstArray);
for LRow := 0 to ASize - 1 do begin for LCol := 0 to ASize - 1 do begin // 以下の式の ASize は列数の値LSrcValue := LpSrcArray^[LRow * ASize + LCol];
LpDstArray^[LRow * ASize + LCol] := LSrcValue * 2.0 ;
end ;end ;end ;
2 次元の動的配列を処理する関数とその関数を使用する例です。
この 2 次元の静的配列との構造の違いにより、2 次元の動的配列を処理すコードでは、2 次元の静的配列は処理できません。その逆に、2 次元の静的配列を処理するコードで 2 次元の動的配列を処理することはできません。
本サンプルの関数を使用する場合は、以下のように、配列の引数にはその配列自身のアドレスを指定しないと正常に処理できません。例外が発生します。
// 最初の配列要素のアドレスではなく、配列のアドレスを渡す SetArrayElement(LSize, @LSrcArray, @LDstArray);
[備考]
図3
リスト10
copy code
unit Unit1;interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
procedure FormCreate(Sender: TObject);procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// フォーム生成時の処理// =============================================================================procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);begin Memo1.Font.Charset := ANSI_CHARSET;
Memo1.Font.Name := 'Courier New' ;
Memo1.Font.Size := 11 ;
end ;// =============================================================================// 2 次元配列の引数をポインタで渡す例// 動的配列の場合// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LSrcArray : array of array of Double;
LDstArray : array of array of Double;
LSize : Integer;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
LText : string ;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.BeginUpdate;
// 配列のサイズを設定LSize := 3 ;
SetLength(LSrcArray, LSize, LSize);
SetLength(LDstArray, LSize, LSize);
// 配列の各要素に値を代入for LRow := Low(LSrcArray) to High(LSrcArray) do begin for LCol := Low(LSrcArray[LRow]) to High(LSrcArray[LRow]) do begin LSrcArray[LRow, LCol] := (LRow + 1 ) * 10 + (LCol + 1 ) + 0.2 ;
end ;end ;// 代入した値を確認表示for LRow := Low(LSrcArray) to High(LSrcArray) do begin LText := '' ;
for LCol := Low(LSrcArray[LRow]) to High(LSrcArray[LRow]) do begin LText := LText + FormatFloat('0.0 ' , LSrcArray[LRow][LCol]);
end ;Memo1.Lines.Add(LText);
end ;// 関数の実行// 本サンプルの関数の処理の場合は,配列自身のアドレスを指定するSetArrayElement(LSize, @LSrcArray, @LDstArray);
// 関数の実行結果しての配列要素の値を表示Memo1.Lines.Add('' );
for LRow := Low(LDstArray) to High(LDstArray) do begin LText := '' ;
for LCol := Low(LDstArray[LRow]) to High(LDstArray[LRow]) do begin LText := LText + FormatFloat('0.0 ' , LDstArray[LRow][LCol]);
end ;Memo1.Lines.Add(LText);
end ;Memo1.Lines.EndUpdate;
end ;// -----------------------------------------------------------------------------// 2 次元配列を引数に持つ関数の例// 引数の配列が Double 型の動的配と仮定した処理例// この関数は動的配列のアドレスを渡さないと正常に処理できない// // Windows API の関数や他の DLL 内の関数の実際の処理は不明// Windoows API の関数は DLL で提供されている// -----------------------------------------------------------------------------function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;var LSrcArrayOrigin : NativeUInt;
LSrcArrayAddr : NativeUInt;
LDstArrayAddr : NativeUInt;
LSrcRowArrayAddr : NativeUInt;
LDstRowArrayAddr : NativeUInt;
LSrcValue : Double;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Result := True;
// 配列のアドレスを逆参照で取得// このアドレスは最初の行の配列のポインタLSrcArrayAddr := PNativeUInt(ASrcArray)^;
LDstArrayAddr := PNativeUInt(ADstArray)^;
// 配列のアドレスを退避LSrcArrayOrigin := LSrcArrayAddr;
for LRow := 0 to ASize - 1 do begin // LRow 行目の配列のアドレスを逆参照で取得// このアドレスはこの行の配列の最初の要素のポインタLSrcRowArrayAddr := PNativeUInt(LSrcArrayAddr)^;
LDstRowArrayAddr := PNativeUInt(LDstArrayAddr)^;
for LCol := 0 to ASize - 1 do begin // 配列要素の値を逆参照で取得// LSrcValue := ASrcArray[LRow][LCol]; の操作LSrcValue := PDouble(LSrcRowArrayAddr)^;
// 配列要素に値を代入// ADstArray[LRow][LCol] := LSrcValue * 2.0; の操作PDouble(LDstRowArrayAddr)^ := LSrcValue * 2.0 ;
// 同じ行の次のデータのある場所 (ポインタ) に移動inc(PDouble(LSrcRowArrayAddr));
inc(PDouble(LDstRowArrayAddr));
end ;// 次の行の配列ポインタに移動inc(PNativeUInt(LSrcArrayAddr));
inc(PNativeUInt(LDstArrayAddr));
end ;end ;end .
上のコードはポインタを連続的に移動して処理しているだけです 。配列に対して汎用的な処理を行うには、以下のように、任意の配列要素への代入や値の取得の機能が必要です。
リスト11
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// 指定要素の値を取得// 引数の ARowAddr は最初の行の配列のアドレス // -----------------------------------------------------------------------------function GetDyn2DDouble(ARowAddr: NativeUInt; ARow, ACol: Integer): Double;var LRowAddr : NativeUInt;
begin // 行方向にポインタをインクリメントして目的の行の配列のアドレスを取得inc(PNativeUInt(ARowAddr), ARow);
LRowAddr := PNativeUInt(ARowAddr)^;
// 列方向にポインタをインクリメントinc(PDouble(LRowAddr), ACol);
// そのポインタにおける値を逆参照で取得Result := PDouble(LRowAddr)^;
end ;// -----------------------------------------------------------------------------// 指定要素に値を代入// -----------------------------------------------------------------------------procedure SetDyn2DDouble(ARowAddr: NativeUInt; ARow, ACol: Integer; AValue: Double);var LRowAddr : NativeUInt;
begin inc(PNativeUInt(ARowAddr), ARow);
LRowAddr := PNativeUInt(ARowAddr)^;
inc(PDouble(LRowAddr), ACol);
PDouble(LRowAddr)^:= AValue;
end ;// -----------------------------------------------------------------------------// 2 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Double 型の動的配列// (2) 配列のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// -----------------------------------------------------------------------------function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;var LSrcArrayAddr : NativeUInt;
LDstArrayAddr : NativeUInt;
LSrcValue : Double;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Result := True;
// 配列のアドレスを逆参照で取得// このアドレスは最初の行の配列のポインタLSrcArrayAddr := PNativeUInt(ASrcArray)^;
LDstArrayAddr := PNativeUInt(ADstArray)^;
for LRow := 0 to ASize - 1 do begin for LCol := 0 to ASize - 1 do begin LSrcValue := GetDyn2DDouble(LSrcArrayAddr, LRow, LCol);
SetDyn2DDouble(LDstArrayAddr, LRow, LCol, LSrcValue * 2.0 );
end ;end ;end ;
Delphi では配列を型定義して使用することができます。Delphi の型定義の動的配列を使用すると、2 次元の動的配列の処理を以下のように書けます。
リスト12
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// 2 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Double 型の動的配列// (2) 配列のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// -----------------------------------------------------------------------------function SetArrayElement(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer): Boolean;type TDyn2DArray = array of array of Double;
PDyn2DArray = ^TDyn2DArray;
var LpSrcArray : PDyn2DArray;
LpDstArray : PDyn2DArray;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
begin Result := True;
// 配列のポインタを取得LpSrcArray := PDyn2DArray(ASrcArray);
LpDstArray := PDyn2DArray(ADstArray);
for LRow := 0 to ASize - 1 do begin for LCol := 0 to ASize - 1 do begin LpDstArray^[LRow][LCol] := LpSrcArray^[LRow][LCol] * 2.0
end ;end ;end ;
上のような処理コードであれば以下のように、配列の行数や列数等が取得てぎす。これらの値を利用すれば、関数の引数に行数や列数の値がなくても処理できます。
// 行数を取得LRowSize := Length(LpSrcArray^);
// 列数を取得 (1 番目の行の配列の要素数)LColSizse := Length(LpSrcArray^[0 ]);
// 行の最小要素番号 (動的配列の場合は常に 0)LValue := Low(LpSrcArray^);
// 行の最大要素番号 )行数 - 1)LValue := High(LpSrcArray^);
Delphi のクラス等の型はポインタです。関数の引数として型定義した配列変数も渡せます。以下のように配列の引数の型として、定義した型のポインタ型も指定できます。
// DLL 内の関数を使用する側の配列の型宣言 Type TDataArray = array [0 ..4 ] of Double;
PDataArray = ^TDataArray;
var Lsrc_dat : TDataArray;
Ldst_dat : TDataArray;
// 引数に型のポインタ型であれば使用できる procedure test_func(ASize: integer; ASrcArray, ADstArray: PDataArray); stdcall ;external 'TestDll.dll' ;
動的配列の場合は以下のように定義した型を指定できます。
procedure test_func(ASize: integer; ASrcArray, ADstArray: TDataArray); stdcall ;external 'TestDll.dll' ;
一般的に、DLL 内の関数は Delphi のクラスの型や、呼び出し側で宣言した型のことを知りません。したがって、実際には DLL 内の関数で定義されている型として処理されます。本ペーに掲載しているサンプルでは Pointer 型として処理されることになります。
行列演算ライブラリ、数値計算ライブラリとして提供されている 2 次元の配列関係の関数の多くは静的配列用です。
C または C++ の関数の定義が以下のようにアドレスを意味する * 演算子が 2 つのポインタのポインタとなっている場合は、2 次元の動的配列のデータ構造を考えると、おそらく動的配列です。静的配列の場合は * 演算子が 1 つだけです。
// 関数のプロトタイプ宣言
void array_sample(double **, int, int);
// 関数の定義void array_sample(double **array, int row, int col)
{
// コードは省略}
不明な場合は、関数を実行する際、次のように配列のアドレスを渡して実際に実行して確認すると確実しかないでしょう。
procedure array_test(ASize: Integer; ASrcArray, ADstArray: Pointer);stdcall ; external 'TestDll.dll' var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // -----------------------------------------------------------------------------// ローカル変数が確保可能なメモリに制限があるのでグローバル変数で確保// -----------------------------------------------------------------------------const FSize = 10 ;
type TDataArray = array [0 ..FSize - 1 ] of array [0 ..FSize - 1 ] of Double;
var FSrcArray : TDataArray;
FDstArray : TDataArray;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);begin FSrcArray := System.Default (TDataArray);
FDstArray := System.Default (TDataArray);
// 関数実行array_test(FSize, @FSrcArray, @FDstArray);
ShowMessage('Close' );
Close;
end ;
テストは静的配列、動的配列のどちらかで十分です。
行列演算用のライブラリや数値計算ライブラリの中には、1 次元の配列を渡すと、内部では 2 次元の配列として処理する関数を実装しているライブラリがあります。この方式であれば、その関数が 1 次元の静的配列用であっても、動的な配列も扱えます。
図4
リスト13
copy code
// =============================================================================// フォーム生成時の処理// =============================================================================procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);begin Memo1.Font.Charset := ANSI_CHARSET;
Memo1.Font.Name := 'Courier New' ;
Memo1.Font.Size := 11 ;
end ;// =============================================================================// 1 次元の配列を 2 次元の配列として操作する例// 動的配列の場合// // 1 次元の配列を 2 次元の配列として扱う関数は、2 次元の静的配列が使用可能// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LSrcArray : array of Double;
LRowSize : Integer;
LColSize : Integer;
LRow : Integer;
LCol : Integer;
LIndex : Integer;
LText : string ;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.BeginUpdate;
// 動的配列のサイズを設定LRowSize := 3 ;
LColSize := 4 ;
SetLength(LSrcArray, (LRowSize * LColSize));
// 配列の各要素に値を代入LIndex := 0 ;
for LRow := 0 to LRowSize - 1 do begin for LCol := 0 to LColSize - 1 do begin LSrcArray[LIndex] := (LRow + 1 ) * 10.0 + (LCol + 1 ) + 0.2 ;
Inc(LIndex);
end ;end ;// 代入した値を確認表示LIndex := 0 ;
for LRow := 0 to LRowSize - 1 do begin LText := '' ;
for LCol := 0 to LColSize - 1 do begin LText := LText + FormatFloat('0.0 ' , LSrcArray[LIndex]);
Inc(LIndex);
end ;Memo1.Lines.Add(LText);
end ;// 2 行 3 列目の値を取得して表示LRow := 1 ;
LCol := 2 ;
LIndex := LRow * LColSize + LCol;
LText := FormatFloat('0.0 ' , LSrcArray[LIndex]);
Memo1.Lines.Add('' );
Memo1.Lines.Add(LText);
// 指定インデック (0 ベース) の行と列番号(0 ベース) を取得して表示LRow := LIndex div LColSize;
LCol := LIndex mod LColSize;
LText := '[' + IntToStr(LRow) + '][' + IntToStr(LCol) + ']' ;
Memo1.Lines.Add('' );
Memo1.Lines.Add(LText);
// 対角要素の値// uses に Math が必要Memo1.Lines.Add('' );
for LCol := 0 to Min(LRowSize, LColSize) - 1 do begin LIndex := LCol * LColSize + LCol;
LText := FormatFloat('0.0 ' , LSrcArray[LIndex]);
Memo1.Lines.Add(LText);
end ;Memo1.Lines.EndUpdate;
end ;
08_ DLL に関数を組み込む - DLL 内の関数の独立性と汎用性
本ページに掲載している関数のコードは同じユニット内に書いていますが、そのまま DLL 内の関数として組み込めるようになっています。
DLL 内の関数は独立した機能で汎用的である必要があります。Integer, Single, Double 等の単純型の型であれば、どのプログラム言語にも実装されているので DLL 内の関数の引数の型として使用できます。また、Windows API で定義済みの構造体 (Delphi ではレコード型) も DLL 内の関数の引数の型として使用できます。
配列にはプログラム言語に共通の型がありません。配列を使用する関数を汎用的にするには、配列を受け取る引数の型をポインタ型にします。関数を使用するアプリは、配列のアドレス、あるいは配列の最初の要素のアドレスをポインタとして渡します。
DLL を使用する側のプログラムにも、DLL 側にも同じ配列の型宣言をしておけば、関数の引数にその型を使用できますが、Delphi 専用の DLL になってしまって汎用的とは言えません。Delphi 専用でいいのであればユニット形式で提供した方が便利です。
09_ DLL に関数を組み込む - DLL の作成方法と使用方法
以下のコードは DLL のプロジェクトのソースコードです。このコードを、拡張子を .dpr にして、コードの先頭の library の名前で保存します。この場合は TestDll.dpr となります。
Delphi で新規にプロジェクトを作成すると、フォーム関係の Unit1.pas, Unit1.dfm ファイルができます。それらのファイルは DLL の作成に必要ありません。削除します
この DLL には関数を 1 つだけ実装しています。関数のコードはこれまでの関数のコードをそのまま使用できますが、関数の最後、末尾に stdcall を追加します。exports 部には、外部から利用する関数名をリストします。それ以外は一般的なユニットで使用する関数の記述と同じです。
stdcall は呼出し規約と言うコンパイラ指令です。これは、コンパイラが関数の引数を処理する時の仕様です。Windows 上で作成する DLL はこの呼び出し規約を使用すると思ってください。
リスト14
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// DLL の作成方法// (1) このコードを TestDll.dpr (library 名 + .dpr) の名前で保存// (2) 保存したファイルを Delphi の IDE で開く// (3) [Shift] + [F9] でコンパイルする// (4) TestDll.dll が作成される// // ※ DLL が作成される場所はプロジェクトの構成によって異なる// ----------------------------------------------------------------------------library TestDll;uses // 必要なら他のユニットを追加するSystem.SysUtils,
System.Classes;
// -----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Double 型の静的配列または動的配列// (2) 配列の最初の要素のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// // 外部から使用する関数には呼び出し規約のコンパイラ指令 stdcall を末尾に追加する// -----------------------------------------------------------------------------procedure array_test(ALen: Integer; ADataArr: Pointer); stdcall ;var Lindex : Integer;
begin // 配列型の引数の型が Pointere になっている// 元の Double 型にするために PDouble 型でキャストする// 配列用要素の値に対する操作は逆参照for Lindex := 0 to ALen - 1 do begin PDouble(ADataArr)^ := (Lindex + 1.0 ) * 100.0 ;
inc(PDouble(ADataArr));
end ;end ;exports // 外部から呼び出して使用する関数名のリストarray_test;
end .
以下は DLL 内の関数を使用したプログラムのコードです。
stdcall ; external 'TestDll.dll'
stdcall は呼出し規約です。DLL 内の関数の呼び出し規約と同じにします。external 宣言は、この関数あるいは手続きを、その右に記述したファイルからインポートして使用するという意味です。
本サンプルで使用する DLL ファイルは、システム的にパスの通った場所に必要です。アプリの EXE が最初に探しにいくのは EXE 自身があるフォルダ内です。
図5
リスト15
copy code
unit Unit1;interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;// DLL 内の関数の使用宣言// DLL (この場合は TestDll.dll) はシステム的にパスの通った場所に必要// アプリが最初に検索する場所はそのアプリの EXE ファイルがあるフォルダ内// プロジェクト関係ファイルと同じ場所に EXE が作成されるとは限らない procedure array_test(ASize: Integer; AArray: Pointer); stdcall ; external 'TestDll.dll' ;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// DLL 内の配列処理関係の関数を使用するコード// 配列の要素数が多いと実行時にメモリアクセス違反の例外が発生する// その場合は配列変数をグローバル変数にする// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LArrayData : array of Double;
LSize : Integer;
LIndex : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.BeginUpdate;
LSize := 5 ;
SetLength(LArrayData, LSize);
// DLL 内の関数を実行array_test(LSize, @LArrayData[0 ]);
for Lindex := 0 to LSize - 1 do begin Memo1.Lines.Add(FloatToStr(LArrayData[LIndex]));
end ;Memo1.Lines.EndUpdate;
end ;end .
配列の引数を、以下のように要素のデータ型に応じたポインタ型にすると関数の処理コードが少しはスッキリします。この方法は静的配列で使用できます。動的配列の場合は PNativeUInt 型にします。
procedure array_test(ALen: Integer; ADataArr: PDouble); stdcall ;var Lindex : Integer;
begin // 配列型の引数の型が PDouble になっている// 呼び出し側で汎用の Pointer で渡せば PDouble 型にキャストされる// したがって以下のようにそのまま値の取得や代入ができる// 配列用要素の値に対する操作は逆参照for Lindex := 0 to ALen - 1 do begin ADataArr^ := (Lindex + 1.0 ) * 100.0 ;
inc(ADataArr);
end ;end ;
Delphi の IDE から DLL を新規に作成するには、[ファイル] [新規作成] で [その他] を選択して下図のダイアログを表示します。このダイアログの [Delphi ファイル] から [ダイナミックリンクライブラリ] を選択します。
上の DLL のプロジェクトのソースコードを保存して生成されるプロジェクトの構成は以下の記事と同じようになります。その構成の設定内容は IDE から新規に DLL のプロジェクトを作成した場合と少し違います。プロジェクトの構成の設定内容は [プロジェクト] [オプション] で変更できます。
図6
[ファイル] [新規作成]
[Delphi ファイル] から [ダイナミックリンクライブラリ] を選択する
10_ DLL に関数を組み込む - 処理コードを別ユニットにする
DLL 内だけで使用する関数も含めて、実装する関数や処理コードが多くなると、ユニットファイルを作成した方が便利です。以下のコードは、処理コードを別のユニットにした場合の DLL のプロジェクトのソースコードです。
リスト16
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// DLL の作成方法// (1) このコードを TestDll.dpr (library 名 + .dpr) の名前で保存// (2) 保存したファイルを Delphi の IDE で開く// (3) [Shift] + [F9] でコンパイルする// (4) TestDll.dll が作成される// // ※ DLL が作成される場所はプロジェクトの構成によって異なる// コンパイルするには TestDll_sub.pas がライブラリのパスが通った場所に必要// ----------------------------------------------------------------------------library TestDll;uses // 必要なら他のユニットを追加するTestDll_sub;
exports // 外部から呼び出して使用する関数名のリストarray_test;
end .
作成したユニットのコードです。実装している機能は前項のサンプルと同じです。
ユニットは、DLL のプロジェクトを開いた状態で、IDE のメニューの [ファイル] [新規作成] から [ユニット] で追加できます。追加したら名前を付けて保存します。下に示すユニットは、TestDll_sub.pas という名前で保存しています。
リスト17
copy code
// ----------------------------------------------------------------------------// DLL のプロジェクトで使用するユニットのコード// このコードを TestDll_sub.pas (unit 名 + .pas) の名前で保存する// 保存先は DLL のプロジェクトファイル (拡張子は .dpr) があるフォルダ内// // ※ プロジェクトの構成によってはプロジェクトのファイルと DLL ファイルが// 別フォルダになることがある// ----------------------------------------------------------------------------unit TestDll_sub;interface uses // 必要に応じて追加するSystem.SysUtils,System.Classes;
// 関数の宣言部// 外部から使用する関数には呼び出し規約のコンパイラ指令 stdcall を末尾に追加するprocedure array_test(ALen: Integer; ADataArr: Pointer); stdcall ;// 外部から使用しない関数にはコンパイラ指令 stdcall は不要function GetValue(ArrayPtr: Pointer; AIndex: Integer): Double;procedure SetValue(ArrayPtr: Pointer; AIndex: Integer; AValue: Double);implementation // 以下、関数の実現部// -----------------------------------------------------------------------------// 1 次元配列を処理する関数の例// // (1) 引数の配列が Double 型の静的配列または動的配列// (2) 配列の最初の要素のアドレスを引数にしている// と仮定した場合の処理例// // 外部から使用する関数には呼び出し規約のコンパイラ指令 stdcall を末尾に追加する// -----------------------------------------------------------------------------procedure array_test(ALen: Integer; ADataArr: Pointer); stdcall ;var Lindex : Integer;
LValue : Double;
begin // 配列型の引数の型が Pointere になっている// 元の Double 型にするために PDouble 型でキャストが必要// 配列用要素の値に対する操作は逆参照for Lindex := 0 to ALen - 1 do begin LValue := GetValue(ADataArr, Lindex);
SetValue(ADataArr, Lindex, (Lindex + 1.0 ) * 100.0 );
end ;end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 指定要素の値を取得// 引数の ArrayPtr は配列の最初の要素のポインタ// // 外部から使用しない関数にはコンパイラ指令 stdcall は不要// ----------------------------------------------------------------------------function GetValue(ArrayPtr: Pointer; AIndex: Integer): Double;begin // 配列の先頭要素からポインタをインクリメントinc(PDouble(ArrayPtr), AIndex);
// そのポインタにおける値を逆参照で取得Result := PDouble(ArrayPtr)^;
end ;// ----------------------------------------------------------------------------// 指定要素に値を代入// // 外部から使用しない関数にはコンパイラ指令 stdcall は不要// ----------------------------------------------------------------------------procedure SetValue(ArrayPtr: Pointer; AIndex: Integer; AValue: Double);begin inc(PDouble(ArrayPtr), AIndex);
PDouble(ArrayPtr)^ := AValue;
end ;end .