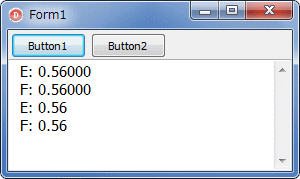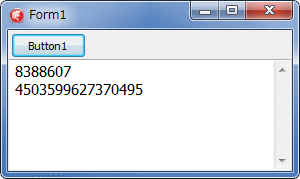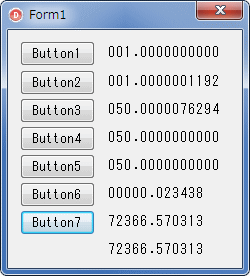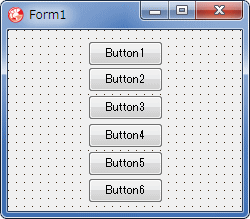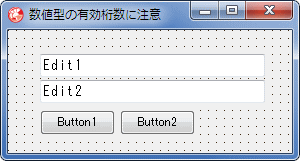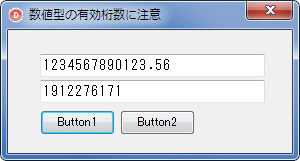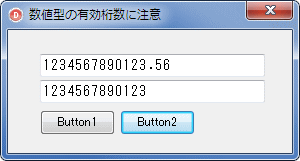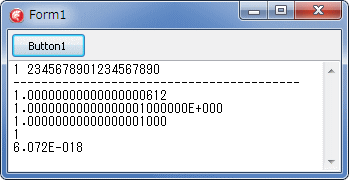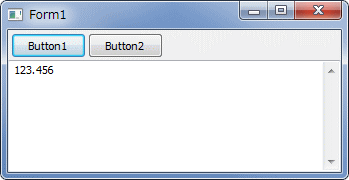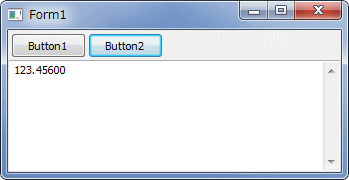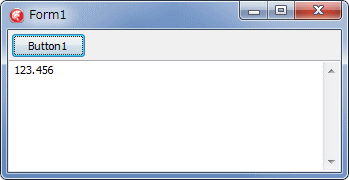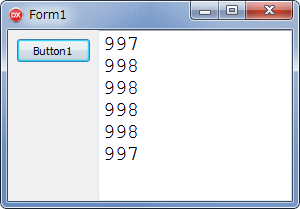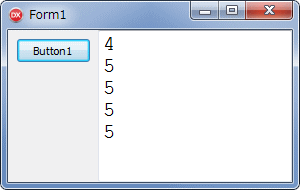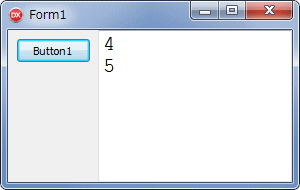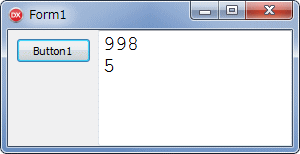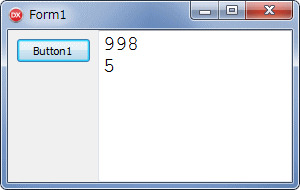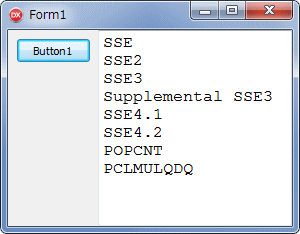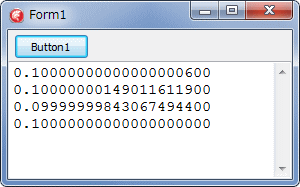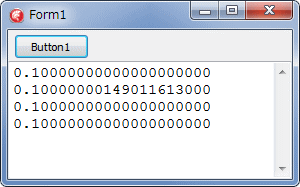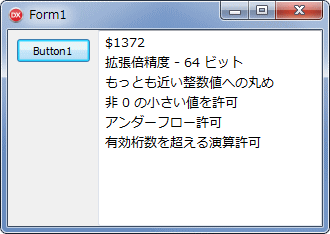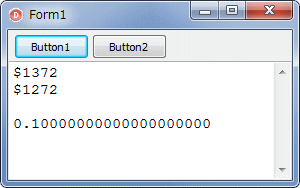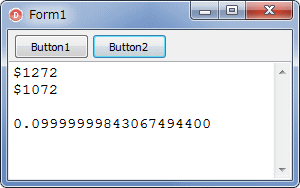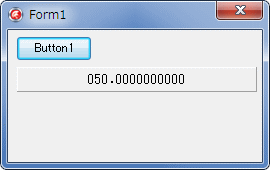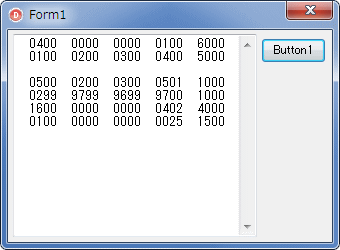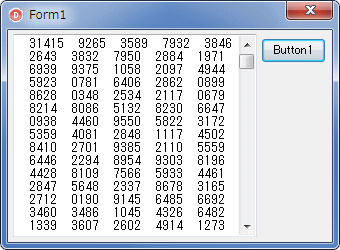Delphi Programming / Object Pascal Delphi サンプルプログラム集
890_計算誤差 ( 数値計算の誤差 ) と多倍長演算
動作確認等
Windows 7 U64(SP1) + Delphi XE(UP1) Pro, 一部は他のバージョンの Delphi
890_CalcError.zip [10,589 KB] 2018年11月24日版 (EXE 同梱)
図の下のコードを見てください。
図1
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var R1 : Single;
begin R1 := 0.1 ;
if R1 = 0.1 then begin MessageBox(Handle, '同じ値です' , '結果' , MB_ICONINFORMATION);
end else begin MessageBox(Handle, '同じ値ではありません' , '結果' , MB_ICONWARNING);
end ;end ;
コミュニティの場で、たまに、計算結果が正しくない、という質問があります。例えば
"0.56" となるハズなのに "0.5600000000000001" になってしまいます "0.56" となるハズなのに "0.5599999999999917" になってしまいます 異なる変数に同じ値が入っているはずなのに、= で比較しても True になりません
というものです。例をあげたらきりがありません。対象の数値や結果は、数値の型や、どんな計算をしたか、結果をどのように取得したかにもよります。必要な有効桁数 を考慮する必要があるということです。
例えば、最初の 2 つの質問の場合、小数点以下 5 桁の精度でよければ、次のようにすれば、どちらの結果も 0.56000, あるいは 0.56 と表示されます。表示桁数の範囲では誤差がないことになります。
図2
FormatFloat 関数で指定桁数だけ表示すると、四捨五入されてどちらも 0.56000 となる
四捨五入して FloatToStr 関数で表示すると、どちらも 0.56 となる
copy code
// =============================================================================// 実数値を四捨五入して表示する例// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var E, F : Double;
begin E := 0.5600000000000001 ;
F := 0.5599999999999917 ;
Memo1.Lines.Add(' E: ' + FormatFloat('##0.00000' , E));
Memo1.Lines.Add(' F: ' + FormatFloat('##0.00000' , F));
// 数値を小数点以下の指定桁で四捨五入する// SimpleRoundTo の使用には uses に Math が必要Memo1.Lines.Add(' E: ' + FloatToStr(SimpleRoundTo(E, -5 )));
Memo1.Lines.Add(' F: ' + FloatToStr(SimpleRoundTo(F, -5 )));
end ;// =============================================================================// 実数値が指定範囲内にあるかを判定する例// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LValue : Single;
LRefVal : Single;
LIncVal : Single;
LCount : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
// 数学的には LValue と LRefVal は同じ値になるLValue := 0.0 ;
for LCount := 1 to 100 0 do begin LValue := LValue + 0.0001 ;
end ;LRefVal := 0.1 ;
// Double 型であれば 1.0E-13 らいまで可能LIncVal := Abs(LRefVal * 1.0E-4 );
if (LValue >= (LRefVal - LIncVal)) and (LValue <= (LRefVal + LIncVal)) then begin Memo1.Lines.Add('範囲内' );
end else begin Memo1.Lines.Add('範囲外' );
end ;end ;
科学技術計算では、長い有効桁数が必要な分野もありますが、多くの場合数桁で十分です。物理的な計測で得られる値が 3 桁の場合、その値を元にした計算結果の精度は、理論的に、3 桁を越えることはできません。
「数学は自然が語りかける言葉」、そしてコンピュータはその数学を実際に計算する道具です。したがって、科学技術計算における数値計算の誤差は重要な課題です。
2.0 精度が小数点以下 1 桁までの場合
01_ 実数値の表現 - コンピュータは有限桁の数値しか扱えない
コンピュータでは、有限桁の数値しか扱えません。
Delphi における実数の内部表現は、IEEE 754 仕様の浮動小数点数形式となっています。4 バイトの実数型 Single の仮数部は 23 ビットで、10 進数では高々 6 桁です。8 バイトの実数型 Double の仮数部は 52 ビットで、10 進数では高々 15 桁です。
図3
4 バイトの実数型は 10 進数で 7 桁まで
8 バイトの実数型は 10 進数で 16 桁まで
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LSingle : UInt64;
LDouble : UInt64;
begin LSingle := $7FFFFF ; // 23 ビットLDouble := $FFFFFFFFFFFFF ; // 52 ビットMemo1.Lines.Add(UIntToStr(LSingle));
Memo1.Lines.Add(UIntToStr(LDouble));
end ;
[備考]
コンピュータの内部では、数値は 2 進数で記憶されます。2 進数は、数値を 0 または 1 で表すものです。この 2 進数の 1 桁を「ビット」と言います。2 進数の 0 と 1 の羅列では冗長でわかりにくいので、通常は、2 進数の 4 桁 (4 ビット) を 1 桁とする 16 進数による表記を使用します。
コンピュータでは、数学でいう分数形式 (有理数) も扱えません。1 / 3 のような分数は、除算の結果として変数に代入することになります。この値は無限小数です。数値の 0.2 も、2 進数、16 進数では無限小数となります。しかし、コンピュータは有限桁しか扱えません。その結果、コンピュータ内部では 0.2 という数値は正確に表現できません。したがって、変数に代入した時点で丸め誤差が発生することになります。
10 進法
2 進法
16 進法
0.1
0.00011001100110011... 0.19999999999...
0.2
0.00110011001100110... 0.33333333333...
0.3
0.01001100110010010... 0.4CCCCCCCCCC...
実数を浮動小数点形数式 ではなく、小数点以下の桁数を限定した 固定小数点数形式 で処理すれば、その桁数だけは正確になります。固定小数点数形式というのは、コンピュータ内部で、整数部の桁数と小数点以下の桁数を固定して処理する実数型のことです。
Delphi では Currency 型が固定小数点数形式となっています。Currency 型では小数点以下 4 桁までを正確に計算することができますが、科学技術計算等で必要な大きな、あるいは小さな数値は扱えません。整数部は約 15 桁までに限られます。
数値計算では、誤差を少なくするためのアルゴリズムがいろいろ考え出されています。
演算誤差を確認するためのテストプログラムです。この記事は計算機の誤差の解析が目的ではありませんので詳しい説明は省略します。実際に体験してみて下さい。
図4
数値の表示には TPanel を使用
Button1 0.1 に 10 を掛けた
Button2 0.1 を 10 回加算
Button3 0.1 を 10 回加算して 50 を掛ける
Button4 Currency 型で Button3 と同じ計算
Button5 BCD 演算で Button3 と同じ計算
Button6 有効桁数が減る例
Button7 積み残しの例(加算しても増加しない)
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Button7: TButton;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
Panel3: TPanel;
Panel4: TPanel;
Panel5: TPanel;
Panel6: TPanel;
Panel71: TPanel;
Panel72: TPanel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);procedure Button2Click(Sender: TObject);procedure Button3Click(Sender: TObject);procedure Button4Click(Sender: TObject);procedure Button5Click(Sender: TObject);procedure Button6Click(Sender: TObject);procedure Button7Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;var Form1: TForm1;
implementation uses FMTBcd;{$R *.dfm} // =============================================================================// 0.1に10を掛ける// Button2Clickのコードと違い、コンパイラが誤差なく計算してくれる。これは言語// の仕様によって異なるので、他のコンパイラでも同じ結果となるとは限らない// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var A : Single;
begin A:=0.1 *10 ;
Panel1.Caption := FormatFloat('000.0000000000' , A);
end ;// =============================================================================// 0.1を10回加算しても数学的に意味の1.0とはならない例// 例えば帳票類で等間隔に罫線を描画する時には注意が必要// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var A : Single;
i : Integer;
begin A := 0.0 ;
for i:=0 to 9 do begin A := A + 0.1 ;
end ;Panel2.Caption := FormatFloat('000.0000000000' , A);
end ;// =============================================================================// ある値(実数値)を整数倍しても必ずしも数学的な整数倍にならない例// 例えばButton2Clickの結果1.0000001192を50倍しても 50.000005960にはならない// =============================================================================procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);var A : Single;
i : Integer;
begin A := 0.0 ;
for i:=0 to 9 do begin A := A + 0.1 ;
end ;A := A * 50 ;
Panel3.Caption := FormatFloat('000.0000000000' , A);
end ;// =============================================================================// Currency 型// DelphiのCurrency型は小数点以下の4桁を整数として格納する固定小数点のデータ型// で、金額計算などでの丸め誤差が少なくなる// 代入文や式で他の実数型と混在させた場合はCurrency型の値に対し自動的に10000で// の除算または乗算が行われる// =============================================================================procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);var A : Currency;
i : Integer;
begin A := 0.0 ;
for i:=0 to 9 do begin A := A + 0.1 ;
end ;A := A * 50 ;
Panel4.Caption := FormatFloat('000.0000000000' , A);
end ;// =============================================================================// FMTBcd.pasのBCD(2進化10進数表記 Binary Coded Decimal)ルーチンを使用すれば// 誤差なく計算できるが非常に面倒// FMTBcdでは4ビットに10進の各桁を保持することにより10進演算を行っている。そ// のため長い桁も少なくとも加減算は誤差なしに扱える// このコードの実行にはusesにFMTBcdが必要// =============================================================================procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);var A : TBcd;
B : TBcd;
i : Integer;
begin A := NullBcd;
B := StrToBcd('0.1' );
for i:=0 to 9 do begin BcdAdd(A, B, A);
end ;BcdMultiply(A, 50 , A);
Panel5.Caption := FormatBcd('000.0000000000' , A);
end ;// =============================================================================// 有効桁数の激減// Singleの有効桁数は7~8桁なので以下の計算では有効桁数が激減してしまう。// =============================================================================procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);var A : Single;
B : Single;
C : Single;
begin A := 72366.573 ;
B := 72366.550 ;
C := A - B;
Panel6.Caption := FormatFloat('00000.000000' , C);
end ;// =============================================================================// 積み残し// Singleの有効桁数は7~8桁なので以下の計算では0.00001は事実上、加算されない// 元のAと加算した結果のCの値は全く同じとなってしまう// =============================================================================procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);var A : Single;
B : Single;
C : Single;
begin A := 72366.573 ;
B := 0.00001 ;
C := A + B;
Panel71.Caption := FormatFloat('00000.000000' , A);
Panel72.Caption := FormatFloat('00000.000000' , C);
end ;end .
上のサンプルとは別の値で、実数型による違いを確認するためのコードです。
図5
数学的に正しい値は以下の通り
Button1 0.1
Button2 0.1
Button3 0.1
Button4 0.1
Button5 0.001
Button6 0.0001
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);procedure Button2Click(Sender: TObject);procedure Button3Click(Sender: TObject);procedure Button4Click(Sender: TObject);procedure Button5Click(Sender: TObject);procedure Button6Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// Single(4バイトの単精度)型の場合// 数値範囲 1.5 x 10^-45 .. 3.4 x 10^38 有効桁数 7~8// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var s : Single;
i : Integer;
begin s := 0 ;
for i := 0 to 9 do s := s + 0.01 ;ShowMessage(FloatToStr(s));
end ;// =============================================================================// Double型(8バイト)の場合// 数値範囲 5.0 x 10^-324 .. 1.7 x 10^308 有効桁数 15~16// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var s : Double;
i : Integer;
begin s := 0 ;
for i := 0 to 9 do s := s + 0.01 ;ShowMessage(FloatToStr(s));
end ;// =============================================================================// Extended型(10バイト)の場合// 数値範囲 3.6 x 10^-4951 .. 1.1 x 10^4932 有効桁数 19~20// =============================================================================procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);var s : Extended;
i : Integer;
begin s := 0 ;
for i := 0 to 9 do s := s + 0.01 ;ShowMessage(FloatToStr(s));
end ;// =============================================================================// Currency型(8バイト)の場合// 数値範囲 -922337203685477.5808.. 922337203685477.5807 有効桁数 19~20// 金額を扱うには十分な桁だろう// =============================================================================procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);var s : Currency;
i : Integer;
begin s := 0 ;
for i := 0 to 9 do s := s + 0.01 ;ShowMessage(CurrToStr(s));
end ;// =============================================================================// Currency型(8バイト)の場合// 数値範囲 -922337203685477.5808.. 922337203685477.5807 有効桁数 19~20// Currency型が扱える小数点以下4桁目の値を加算// =============================================================================procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);var s : Currency;
i : Integer;
begin s := 0 ;
for i := 0 to 9 do s := s + 0.0001 ;ShowMessage(CurrToStr(s));
end ;// =============================================================================// Currency型(8バイト)の場合// 数値範囲 -922337203685477.5808.. 922337203685477.5807 有効桁数 19~20// Currency型が扱える範囲を越えた小数点以下5桁目の値を加算// =============================================================================procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);var s : Currency;
i : Integer;
begin s := 0 ;
for i := 0 to 9 do s := s + 0.00001 ;ShowMessage(CurrToStr(s));
end ;end .
整数型の有効桁数による桁落ちの例です。このような単純な計算であれば、すぐ気づきますが、複雑で計算コードが大量にある場合、擬似乱数もそうですが、このようなことに注意しないと、もしかしたら物理学上の新発見をしてしまうかも知れません。
図6
図7
上の Edit の値を Extended 型の変数に代入後、整数型の Integer 型で整数にする
桁落ちして、とんでもない値となる
図8
上の Edit の値を Extended 型の変数に代入後、整数型の Int64 型で整数にする
桁落ちなしで、正常な結果となる
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);procedure Button2Click(Sender: TObject);procedure FormShow(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;var Form1: TForm1;
implementation {$R *.dfm} // =============================================================================// 変換元の値をセット// =============================================================================procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);begin Edit1.Text := '1234567890123.56' ;
end ;// =============================================================================// 桁落ちの例// Extended型の数値をTrunc関数で整数にしてみる// Extended型の扱える桁数よりも、Integer(32bit)が扱える有効桁数は少ない// したがって結果はとんでもない値となる// // 整数型の説明はヘルプの[整数型]で// 実数型の説明はヘルプの[実数型]で// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var Ret : Integer;
Value : Extended;
begin // 文字列を実数に変換Value := StrToFloat(Edit1.Text);
// 整数に変換Ret := Trunc(Value);
Edit2.text := IntToStr(Ret);
end ;// =============================================================================// 桁落ちしないように整数を64bitにして有効桁数を確保する// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var Ret : Int64;
Value : Extended;
begin // 文字列を実数に変換Value := StrToFloat(Edit1.Text);
// 整数に変換Ret := Trunc(Value);
Edit2.text := IntToStr(Ret);
end ;end .
浮動小数点演算の誤差は避けられないことを説明しました。実際のコードでは、できるだけ誤差を避けるため、例えば途中の計算結果を、一定の桁数で丸めて、精度を変えてしまうことも有効な手段ではないかと思います。
SimpleRoundTo は、指定桁数で、いわゆる算術型丸め、四捨五入した値を返します。
浮動小数点値を文字列にする関数類には、指定精度、桁数で、あるいは書式を整えて文字列にする関数もあります。例えば、FloatToStr 関数は、数値を 15 桁で丸めて、有効桁数 15 の汎用数値形式で文字列に変換します。汎用数値形式では、有効桁内の末尾の 0 は出力しません。
FormatFloat 関数は、単一の数値を、書式を指定して文字列にします。Format 関数は、複数の数値や文字列も含めた値を、書式設定して文字列にする汎用の文字列作成用関数です。もちろん、単一の数値の場合でも利用可能です。
32 ビットアプリケーションの場合、Extended 型は、10 進数で 18 桁以上 (約 20 桁) の値を格納できますが、ForamtFloat 関数や Str 関数を使用して文字列にしても、四捨五入した 18 桁までの値しか取得できません。桁の精度を指定する関数も、Double 型で 15 桁まで、Extended 型では 18 桁までとなっています。
下の図とコードは、それを確認したものです。
図9
18 桁までしか取得できない
1 は FloatToStr での結果
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var E : Extended;
StrText : String ;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Font.Name := 'MS ゴシック' ;
Memo1.Font.Size := 10 ;
Memo1.Lines.Add('1 2345678901234567890' );
Memo1.Lines.Add('-----------------------------------------' );
E := 1.00000000000000000612 ;
Memo1.Lines.Add('1.00000000000000000612' );
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('0.00000000000000000000000E+000' , E));
System.Str(E: 22 : 20 , StrText);
Memo1.Lines.Add(StrText);
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(E));
E := E - 1.0 ;
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('0.000E+000' , E));
end ;
Trunc 関数を使用して、小数点以下を四捨五入した実数値を取得するには工夫が必要です。
copy code
function Roundoff(X: Extended): Integer;begin if X >= 0 then Result := Trunc(X + 0.5 )else Result := Trunc(X - 0.5 );end ;
SimpleRoundTo 関数を使用すれば、以下のように処理できます。SimpleRoundTo 関数は内部で、上のコードと同様の処理を行っています。
function Roundoff(X: Extended): Integer;begin Result := SimpleRoundTo(X, 0 );
end ;
任意の桁で四捨五入、切り捨てや切り上げする方法は、以下の記事を参考にしてください。
Delphi XE3 で実装された TStringHelper には数値を文字列に変換する Parse というメソッドがあります。下のコードはその使用例です。TStringHelper には Format というメソッドがありますが、ここでは FormatFloat 関係を使用して書式を設定しています。
図10
図11
copy code
// =============================================================================// 数値を文字列に変換// 書式が必要なければTStringHelperが使用できる(Delphi XE3 以降専用// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
LText : string ;
begin LValue := 123.456 ;
LText := string .Parse(LValue);
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add(LText);
end ;// =============================================================================// 数値を文字列に変換// 書式が必要な場合// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
LText : string ;
begin LValue := 123.456 ;
LText := FormatFloat('#0.00000' , LValue);
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add(LText);
end ;
[備考]
数値を文字列に変換するのではなく、文字列を数値に変換するには以下のような関数があります。
Delphi XE3 で実装れた TStringHelper には、以下のオンラインヘルプの記事のように、文字列を各種の数値型の値に変換するメソッドがあります。
図12
copy code
// =============================================================================// TStringHelperのメソッドを使用して文字列を数値に変換// TStringHelperには文字列各種の型の数値に変換するメソッド類がある// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LValue : Double;
LText : string ;
begin LText := '123.456' ;
LValue := LText.ToDouble(LText);
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('#0.000' , LValue));
end ;
08_関数の引数が、数値を使用した式の時に発生する現象
関数の引数には変数を使用するのが基本です。引数に具体的な数値が存在する計算式を使用すると期待した結果にならないことがあります。
この現象は主に、引数が算術式を含む「式」の場合に、その演算がどのように処理されるかの問題です。したがって、このような現象は Trunc 関数以外でも発生することがあります。
図13
copy code
// =============================================================================// Trunc関数(小数点以下を切り捨て)の挙動// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LInteger : Integer;
LDouble : Double;
begin Memo1.Lines.Clear;
LInteger := Trunc(9.98 * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 数値を明示的に実数型とする場合LInteger := Trunc(9.98 * 100.0 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 計算結果の値を実数型の変数に代入してからTrunc関数の引数とする場合LDouble := 9.98 * 100 ;
LInteger := Trunc(LDouble);
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 各々の数値をそれぞれの型の変数に代入してからTrunc関数の引数とする場合LDouble := 9.98 ;
LInteger := 100 ;
LInteger := Trunc(LDouble * LInteger);
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 末尾の桁の値が 6 の場合LDouble := 9.9799999999999996 ;
LInteger := Trunc(LDouble * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 末尾の桁の値が 5 の場合LDouble := 9.9799999999999995 ;
LInteger := Trunc(LDouble * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
end ;
次も Trunc 関数の例ですが、上のサンプルと数値が異なる例です。上のサンプルと同じ現象が発生することが確認できます。
図14
copy code
// =============================================================================// Trunc関数(小数点以下を切り捨て)の挙動// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LInteger : Integer;
LIntegerB : Integer;
LDouble : Double;
begin Memo1.Lines.Clear;
// この結果は 4。これ以降の計算結果は全て 5LInteger := Trunc(5 * 0.01 * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 数値を明示的に実数型とする場合LInteger := Trunc(5.0 * 0.01 * 100.0 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 数値の大きい値の順に計算する場合LInteger := Trunc(100 * 5 * 0.01 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 計算結果の値を実数型の変数に代入してからTrunc関数の引数とする場合LDouble := 5 * 0.01 * 100 ;
LInteger := Trunc(LDouble);
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 各々の数値をそれぞれの型の変数に代入してからTrunc関数の引数とする場合LInteger := 5 ;
LIntegerB := 100 ;
LDouble := 0.01 ;
LInteger := Trunc(LInteger * LDouble * LIntegerB);
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
end ;
上のサンプルのような現象は、関数の引数である数値の型が具体的に指定されていないことと、コンピュータが有限の桁数の数値しか扱えないために発生します。
図15
copy code
// =============================================================================// Trunc関数(小数点以下を切り捨て)の挙動// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LInteger : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
// 引数の値を小数点以下 19 桁目で四捨五入// この計算式の場合は小数点以下 19 桁目は実際にはないLInteger := Trunc(SimpleRoundTo((5 * 0.01 * 100 ), -19 ));
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
// 引数の値を小数点以下 10 桁目で四捨五入LInteger := Trunc(SimpleRoundTo((5 * 0.01 * 100 ), -10 ));
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
end ;
数値計算では有効桁数が長いほど、より数学的な計算結果に近い値が得られます。このことは、これまでのテストの結果でも確認しています。
もちろんですが、関数の引数に具体的な数値を使用することを勧めているわけではありせん。関数の引数には、型を指定した変数を使用するのが基本です。
図16
copy code
// =============================================================================// Trunc関数(小数点以下を切り捨て)の挙動// 64 ビットの EXE の場合// // Delphi XE 5(UP2) Pro : 997 と 4 になる// Delphi XE 7 Pro : 998 と 5 になる// Delphi 10.2.3 Community : 998 と 5 になる// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LInteger : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
LInteger := Trunc(9.98 * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
LInteger := Trunc(5 * 0.01 * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
end ;
SSE 等の機能は、それらの機能を実装している CPU であれば、32 ビットの EXE でも利用できます。以下はその例です。作成した MyTrunc という名前の関数の引数に、上のテストで使用した 2 つの計算式を書いて実行しています。どちらも期待した値となっています。
このサンプルコードは Delphi XE2 以降用です。インラインアセンブラで SSE, SSE2 関係の CPU 命令が使用可能になったのは Delphi XE2 からです。
図17
copy code
// -----------------------------------------------------------------------------// ストリーミング SIMD 拡張命令 (SSE) を使用した Trunc 関数// SSE, SSE2,... 関係等の命令セットは Delphi XE2 以降で使用可能// // CVTTSD2SI : Double 値を 64ビット整数値へ変換// EAX : 演算結果の格納用レジスタ (80386以降用)// -----------------------------------------------------------------------------function MyTrunc(const X: Double): Integer;asm CVTTSD2SI EAX, [X]
end ;// =============================================================================// Trunc関数(小数点以下を切り捨て)の挙動// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LInteger : Integer;
begin Memo1.Lines.Clear;
LInteger := MyTrunc(9.98 * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
LInteger := MyTrunc(5 * 0.01 * 100 );
Memo1.Lines.Add(IntToStr(LInteger));
end ;
現在のシステムで使用可能な SSE 関係の機能は、TestSSE 関数で調べることができます。下図は筆者の環境における結果です。
図18
copy code
implementation uses Math;
{$R *.dfm} // =============================================================================// 使用中のコンピュータの SSE(ストリーミング SIMD 拡張命令)機能の確認// usesにMathが必要// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LRes : Cardinal;
begin LRes := TestSSE;
Memo1.Lines.Clear;
if (LRes and seSSE) = seSSE then Memo1.Lines.Add('SSE' );if (LRes and seSSE2) = seSSE2 then Memo1.Lines.Add('SSE2' );if (LRes and seSSE3) = seSSE3 then Memo1.Lines.Add('SSE3' );if (LRes and seSSSE3) = seSSSE3 then Memo1.Lines.Add('Supplemental SSE3' );if (LRes and seSSE41) = seSSE41 then Memo1.Lines.Add('SSE4.1' );if (LRes and seSSE42) = seSSE42 then Memo1.Lines.Add('SSE4.2' );if (LRes and sePOPCNT) = sePOPCNT then Memo1.Lines.Add('POPCNT' );if (LRes and seAESNI) = seAESNI then Memo1.Lines.Add('AES' );if (LRes and sePCLMULQDQ) = sePCLMULQDQ then Memo1.Lines.Add('PCLMULQDQ' );end ;
09_FPU のコントロールワード ( 制御ワード ) と SafeLoadLibrary
浮動小数点の演算の結果は FPU のコントロールワード (制御ワード) によっても異なることがあります。以下のその 1 つの例です。
図19
Delphi XE7 以降でコンパイルした 64 ビットの EXE は SSE 関係のレジスタを使用します。FPU のレジスタは使用しません。したがって、Set8087CW で FPU の制御ワードを変更しても演算の精度が変わることはありません。
図20
浮動小数点の演算に FPU のレジスタを使用しないので制御ワードの設定は無視される
SSE では 128 ビットのレジスタが使われる
Double 型の 0.1 が、表示桁数の範囲内では全て 0 となっている
copy code
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var R1 : Double;
R2 : Single;
begin Memo1.Lines.Clear;
Set8087CW(Default8087CW);
R1 := 0.1 ;
R2 := 0.1 ;
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('##0.00000000000000000000' , R1));
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('##0.00000000000000000000' , R2));
Set8087CW($1072);
R1 := 0.1 ;
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('##0.00000000000000000000' , R1));
Set8087CW($1272);
R1 := 0.1 ;
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('##0.00000000000000000000' , R1));
end ;
FPU の精度制御モード、現在の浮動小数点丸めモード、例外処理の値は、浮動小数点数制御ルーチンの関数類を使用して個別に取得または設定できます。以下は取得の例です。
[備考]
図21
copy code
implementation uses Math;
{$R *.dfm} // =============================================================================// FPU の現在の制御モードを取得// このコードは Delphi XE ではコンパイルできない// // usesにMathが必要// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LFPUPrecis : TFPUPrecisionMode;
LRoundMode : TRoundingMode;
LExceptions : TFPUExceptionMask;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add('$' + IntToHex(Get8087CW, 4 ));
LFPUPrecis := GetPrecisionMode;
if LFPUPrecis = pmSingle then Memo1.Lines.Add('単精度 - 24 ビット' );if LFPUPrecis = pmDouble then Memo1.Lines.Add('倍精度 - 53 ビット' );if LFPUPrecis = pmExtended then Memo1.Lines.Add('拡張倍精度 - 64 ビット' );LRoundMode := GetRoundMode;
if LRoundMode = rmNearest then Memo1.Lines.Add('もっとも近い整数値への丸め' );if LRoundMode = rmDown then Memo1.Lines.Add('切り下げ' );if LRoundMode = rmUp then Memo1.Lines.Add('切り上げ' );if LRoundMode = rmTruncate then Memo1.Lines.Add('切り捨て' );LExceptions := GetFPUExceptionMask;
if exInvalidOp in LExceptions then Memo1.Lines.Add('無効な演算を無視' );if exDenormalized in LExceptions then Memo1.Lines.Add('非 0 の小さい値を許可' );if exZeroDivide in LExceptions then Memo1.Lines.Add('0 による除算許可' );if exOverflow in LExceptions then Memo1.Lines.Add('オーバーフロー許可' );if exUnderflow in LExceptions then Memo1.Lines.Add('アンダーフロー許可' );if exPrecision in LExceptions then Memo1.Lines.Add('有効桁数を超える演算許可' );end ;
上のコードに次のコードを追加すれば、Delphi 6 以降でコンパイルできます。
copy code
implementation {$R *.dfm} type TFPUPrecisionMode = (pmSingle, pmReserved, pmDouble, pmExtended);
TRoundingMode = (rmNearest, rmDown, rmUp, rmTruncate);
TFPUException = (exInvalidOp, exDenormalized, exZeroDivide,
exOverflow, exUnderflow, exPrecision);
TFPUExceptionMask = set of TFPUException;
// ----------------------------------------------------------------------------- // 精度制御の値は9,10ビット目にあるのでシフトして 3(2進数の11)でANDして取得 // ----------------------------------------------------------------------------- function GetPrecisionMode: TFPUPrecisionMode;begin Result := TFPUPrecisionMode((Get8087CW shr 8 ) and 3 );
end ;// ----------------------------------------------------------------------------- // 丸め制御の値は11,12ビット目にあるのでシフトして 3(2進数の11)でANDして取得 // ----------------------------------------------------------------------------- function GetRoundMode: TRoundingMode;begin Result := TRoundingMode((Get8087CW shr 10 ) and 3 );
end ;// ----------------------------------------------------------------------------- // 例外フラグの値は1から6ビット目にあるので3F(2進数の111111)でANDして取得 // ビットが立っている(1である)と該当例外がマスクされている // ----------------------------------------------------------------------------- function GetFPUExceptionMask: TFPUExceptionMask;begin Byte(Result) := Get8087CW and $3F ;
end ;
サードパーティが提供しているライブラリ等では、この FPU の制御ワードを変更する場合があります。例えば、オンラインヘルプにも記述があるように、 OpenGL では変更しています。
以下はエクセルクリエータ 3.0 (Excel Creator 3.0) の DLL をロードする例です。
図22
FPU の制御ワードの値が変更されている
$1372 は Delphi のデフォルトの値
図23
FPU の制御ワードの値が、DLL をロードする前に設定した値のままとなっている
この図は Button1 をクリックした後に Button2 をクリックした結果
リスト20
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
Button2: TButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);procedure Button1Click(Sender: TObject);procedure Button2Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } FDllName : string ;
end ;var Form1: TForm1;
implementation uses Math;
{$R *.dfm} // =============================================================================// フォーム生成時の処理// ロードする DLL のファイル名を設定// =============================================================================procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);begin FDllName := 'XlsCrt2.DLL' ;
end ;// =============================================================================// LoadLibrary 関数で DLL をロードする場合// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var LDllHandle : THandle;
LOldCtrlWord : Word;
LNewCtrlWord : Word;
LRValue : Double;
begin LOldCtrlWord := Get8087CW;
// これが現在の設定値になるSet8087CW($1072 );
LDllHandle := LoadLibrary(PChar(FDllName));
try // 現在の設定値を取得// LoadLibrary で現在の設定値が変わるLNewCtrlWord := Get8087CW;
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add('$' + IntToHex(LOldCtrlWord, 4 ));
Memo1.Lines.Add('$' + IntToHex(LNewCtrlWord, 4 ));
LRValue := 0.1 ;
Memo1.Lines.Add('' );
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('##0.00000000000000000000' , LRValue));
finally FreeLibrary(LDLLHandle);
end ;end ;// =============================================================================// SafeLoadLibrary 関数で DLL をロードする場合// =============================================================================procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var LDllHandle : THandle;
LOldCtrlWord : Word;
LNewCtrlWord : Word;
LRValue : Double;
begin LOldCtrlWord := Get8087CW;
// これが現在の設定値になるSet8087CW($1072 );
LDllHandle := SafeLoadLibrary(PChar(FDllName));
try // 現在の設定値を取得// SafeLoadLibrary では設定値は変しないLNewCtrlWord := Get8087CW;
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add('$' + IntToHex(LOldCtrlWord, 4 ));
Memo1.Lines.Add('$' + IntToHex(LNewCtrlWord, 4 ));
LRValue := 0.1 ;
Memo1.Lines.Add('' );
Memo1.Lines.Add(FormatFloat('##0.00000000000000000000' , LRValue));
finally FreeLibrary(LDLLHandle);
end ;end ;end .
[03_演算誤差のテスト] のサンプルでは、BCD 演算は専用の関数を使用していました。Delphi XE2 では、BCD 演算にも通常の算術演算子が使用できるようになりました。
図24
リスト21
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Button1: TButton;
Panel1: TPanel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;var Form1: TForm1;
implementation uses Data.FMTBcd;{$R *.DFM} // =============================================================================// Delphi XE2以降のBCD演算// 通常の算術演算子が使用可能// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var A : TBcd;
B : TBcd;
i : Integer;
begin A := 0 ;
B := 0.1 ;
for i := 0 to 9 do begin A := A + B;
end ;A := A * 50 ;
Panel1.Caption := FormatBcd('000.0000000000' , A);
end ;end .
コンピュータで扱える数値の桁は有限で、多くの場合 64 ビット ( 10 進で 18 桁程度)までです。
整数の多倍長の四則演算用の関数と、マクローリン展開式を用いた Arctan (逆正接) の値を計算する関数を作成してみました。次のサンプルは、それらを使用したテストです。ListOut で、TStringList に計算結果を格納して、それを TMemo に表示します。
図25
10 進で 20 桁の演算を実行
上の 2 つの値に対して
加算すると、0500 0200... 以下省略
次が減算の結果
次が最初の値に 4 を掛けた結果
最後は最初の値を 4 で割った結果
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Memo1: TMemo;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;var Form1: TForm1;
implementation uses plLongDigit, MMSystem;{$R *.dfm} { TForm1 } // =============================================================================// 多倍長計算ユニットplLongDigitのテスト// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var A : array of Integer;
B : array of Integer;
C : array of Integer;
I : Integer;
M : Integer;
N : Integer;
SL : TStringList;
begin M := 10000 ; // 万進法N := 5 ; // 万進法で5桁SetLength(A, N + 1 );
SetLength(B, N + 1 );
SetLength(C, N + 1 );
for I := 0 to N do begin A[I] := 0 ;
B[I] := 0 ;
C[I] := 0 ;
end ;// 4000000000001006000をセットA[5 ] := 400 ; // 万進法の5桁目A[4 ] := 0 ; // 万進法の4桁目A[3 ] := 0 ; // 万進法の3桁目A[2 ] := 100 ; // 万進法の2桁目A[1 ] := 6000 ; // 万進法の1桁目// 1000200030004005000をセットB[5 ] := 100 ; // 万進法の5桁目B[4 ] := 200 ; // 万進法の4桁目B[3 ] := 300 ; // 万進法の3桁目B[2 ] := 400 ; // 万進法の2桁目B[1 ] := 5000 ; // 万進法の1桁目Memo1.Lines.Clear;
SL := TStringList.Create;
// 元の値をリストListOut (A, M, N, SL);
ListOut (B, M, N, SL);
SL.Add(' ' );
try // 加算Tasu (A, B, C, M, N);
ListOut(C, M, N, SL);
// 減算Hiku (A, B, C, M, N);
ListOut (C, M, N, SL);
// 乗算Kakeru (A, 4 , C, M, N);
ListOut (C, M, N, SL);
// 除算Waru (A, 4 , C, M, N);
ListOut (C, M, N, SL);
Memo1.Text := SL.Text;
finally FreeAndNil(SL);
end ;end ;end .
作成した整数の多倍長の四則演算用の関数と、マクローリン展開式を用いた Arctan (逆正接) の値を計算するコードです。 plLongDigit.pas という名前のユニットにしています。
リスト23
copy code
unit plLongDigit;interface uses SysUtils, Classes, Forms;
procedure Tasu (A,B : array Of Integer; var C: array of Integer; M,N :Integer);procedure Hiku (A,B : array Of Integer; var C: array of Integer; M,N :Integer);procedure Kakeru (A: array of Integer; B: Integer; var C: array of Integer;M, N: Integer);
procedure Waru (A: array of Integer; B: Integer; var C: array of Integer;M, N: Integer);
procedure AT(Bunbo,Kousu: Integer; var C: array of Integer; M,N: Integer);procedure ListOut (A: array of Integer; M,N: Integer; SL : TStringList);implementation uses Math;// -----------------------------------------------------------------------------// M進法N桁の加算(Mは10の整数乗)// M進法N桁の数A,Bを配列A,Bに記録。その和Cを計算する// -----------------------------------------------------------------------------procedure Tasu(A,B: array of Integer; var C:array of Integer; M,N:Integer);var CK : Integer;
K : Integer;
IC : Integer;
begin IC := 0 ;
for K := 1 to N do begin CK := A[K] + B[K] + IC ;
if CK >= M then begin CK := CK - M;
IC := 1 ;
end else begin IC := 0 ;
end ;C[K] := CK;
Application.ProcessMessages;
end ;end ;// -----------------------------------------------------------------------------// M進法N桁の引き算(Mは10の整数乗)// M進法N桁の数A,Bを配列A,Bに記録。その差A-Bをを計算しCに格納する// -----------------------------------------------------------------------------procedure Hiku(A,B:array of Integer; var C:array of Integer; M,N:Integer);var IB : Integer;
AK : Integer;
BK : Integer;
K : Integer;
begin IB := 0 ;
for K := 1 to N do begin AK := A[K];
BK := B[K] + IB;
if AK < BK then begin AK := AK + M;
IB := 1 ;
end else begin IB := 0 ;
end ;C[K] := AK - BK;
Application.ProcessMessages;
end ;end ;// -----------------------------------------------------------------------------// M進法N桁の乗算(Mは10の整数乗)// M進法N桁の数AとM進法1桁の数Bの積を計算し、その結果を配列Cに格納する// 数Bを大きな桁にすると大変な桁になってしまう。1桁ならM進法で1桁増加のみ// -----------------------------------------------------------------------------procedure Kakeru(A: array of Integer; B: Integer; var C: array of Integer;M, N: Integer);
var CK : Integer;
IC : Integer;
K : Integer;
begin IC := 0 ;
for K := 1 to N do begin CK := A[K] * B + IC;
if K <> N then begin if CK >= M then begin IC := CK div M;
CK := CK -IC * M;
end else begin IC := 0 ;
end ;end ;C[K] := CK;
Application.ProcessMessages;
end ;end ;// -----------------------------------------------------------------------------// M進法N桁の乗算(Mは10の整数乗)// M進法N桁の数AをM進法1桁の数Bで割り、その結果を配列Cに格納する// -----------------------------------------------------------------------------procedure Waru(A: array of Integer; B: Integer; var C: array of Integer;M, N: Integer);
var P : Integer;
Q : Integer;
R : Integer;
K : Integer;
begin R := 0 ;
for K := N downto 1 do begin P := A[K] + R * M;
Q := P div B;
R := P - Q * B;
C[K] := Q;
Application.ProcessMessages;
end ;end ;// -----------------------------------------------------------------------------// M進法N桁の関数例(Mは10の整数乗)// 逆正接の値を多倍長の級数計算でKousu項まで求め、結果を配列Cに格納する// 計算はテイラー展開式。CPUのFPU(浮動小数点演算ユニット)では超越関数と呼ばれ// ている関数をこのような計算で求めている。ただしarctanの算出アルゴリズにこれ// が使用されているとか限らない// 計算するのはarctan(1/Bunbo)の値// -----------------------------------------------------------------------------procedure AT(Bunbo, Kousu: Integer; var C: array of Integer; M,N: Integer);var H : Integer;
BB : Integer;
I : Integer;
KOU : Integer;
A : array of Integer;
B : array of Integer;
begin H := 3 ;
BB := Bunbo * Bunbo;
SetLength(A, N + 1 );
SetLength(B, N + 1 );
for I := 0 to N do begin C[I] := 0 ;
end ;A[N] := M;
Waru (A, Bunbo, A, M, N);
Tasu (C, A, C, M, N);
for KOU := 1 to (Kousu div 2 ) do begin Waru (A, BB, A, M, N);
Waru (A, H, B, M, N);
Hiku (C, B, C, M, N);
H := H + 2 ;
Waru (A, BB, A, M, N);
Waru (A, H, B, M, N);
Tasu (C, B, C, M, N);
H := H + 2 ;
end ;end ;// -----------------------------------------------------------------------------// M進法N桁の値をTStringListに格納(Mは10の整数乗)// 万進法であれば10進で4桁ごとに区切り、1行はM進法で5桁とする// Log10の使用にはusesにMathが必要// -----------------------------------------------------------------------------procedure ListOut(A: array of Integer; M,N: Integer; SL : TStringList);var I : Integer;
J : Integer;
L : Integer;
Str : String ;
Fmt : String ;
Keta : Integer;
begin Keta := Trunc(Log10(M));
Fmt := StringOfChar('0' , Keta);
I := N;
for L := 1 to (N div 5 ) + 1 do begin Str := '' ;
for J := 1 to 5 do begin Str := Str + ' ' + FormatFloat(Fmt, A[I]);
I := I - 1 ;
if I = 0 then begin SL.Add(Str);
exit;
end ;end ;SL.Add(Str);
end ;end ;end .
12_ 円周率 π の値を 10,000 桁まで計算
多倍長演算のルーチンを作成しましたので、実際の使用例として円周率 π の値を計算してみることにします。万進法で 10,000 桁まで計算します。π の計算には以下のマチンの公式を用いています。
ほとんどのコンピュータでは何秒もかからないでしょう。筆者の環境では 2278 ms でした。変数 Keta の値を変更するだけで計算桁数を変更することができます。
図26
リスト24
copy code
unit Unit1;interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type TForm1 = class (TForm)
Memo1: TMemo;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);private { Private 宣言 } public { Public 宣言 } end ;var Form1: TForm1;
implementation uses plLongDigit, MMSystem;{$R *.dfm} { TForm1 } // =============================================================================// マチンの公式を用いてπの値を10,000桁まで計算する// 多倍長計算として、万進法(1桁が10進の4桁)を使用// M進法の最後の桁はまるめ誤差のため厳密な値ではない// // TimeGetTimeにはusseにMMSystemが必要// =============================================================================procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var M : Integer;
N : Integer;
Keta : Integer;
Kou5 : Integer;
Kou239 : Integer;
X : array of Integer;
XX : array of Integer;
Y : array of Integer;
Z : array of Integer;
ZZ : array of Integer;
TStart : DWORD;
TEnd : DWORD;
SL : TStringList;
begin Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Update;
TStart := TimeGetTime;
// 計算するπの桁数Keta := 10000 ;
M := 10000 ; // 万進法N := Keta div 4 ; // 万進法でN桁// arctanの計算に必要なテイラー展開式の概略項数Kou5 := Trunc((Keta * 1.403 ) / 2 );
Kou239 := Trunc((Keta * 0.421 ) / 2 );
Kou5 := Kou5 + Kou5 div 10 ;
Kou239 := Kou239 + Kou239 div 10 ;
SetLength (X, N+1 );
SetLength (XX, N+1 );
SetLength (Y, N+1 );
SetLength (Z, N+1 );
SetLength (ZZ, N+1 );
// arctan(1/5)の値をテイラー展開のKou5まで計算して配列Xに格納。それに4を掛けるAT (5 , Kou5, X, M, N);
Kakeru (X, 4 , XX, M, N);
// arctan(1/239)の値をテイラー展開のKou239まで計算して配列Yに格納AT (239 , Kou239, Y, M, N);
Hiku (XX, Y, Z, M, N);
Kakeru (Z, 4 , ZZ, M, N);
TEnd := TimeGetTime;
// 結果を表示SL := TStringList.Create;
try ListOut (ZZ, M, N, SL);
SL.Add (' ' );
SL.Add (IntToStr(TEnd-TStart)+' ms ' );
Memo1.Text := SL.Text;
finally FreeAndNil(SL);
end ;end ;end .