|
Delphi Programming / Object Pascal
  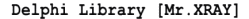
[掲載 2000年05月07日] [更新 2020年01月04日] PC-9801 目次 |
PC-9801
コルトマンの換算式による空間周波数伝達関数 Ver.2.1 |
| 動作確認等 |
掲載の図は、Windows 2000 + Anex86 での実行結果 |
 |
COLTDEMO.zip [939 KB] (Ver. 2.1) |
矩形波チャートの出力のコントラスト比から X 線撮影系の MTF を計算する方法があります。この時に使用するのがコルトマンの換算式と呼ばれる級数展開式です。コルトマンの換算式を使用すると、入力波形と出力波形の周波数解析を必要としません。矩形波の出力をフーリェ変換しなくても X 線撮影系の MTF を計算することができます。。
このプログラムは、このコルトマンの換算式の項数と伝達関数の計算結果の誤差の関係を調べるためのものです。
|
このプログラムでは、次の手順で曲線をプロットしていきます。
- 空間周波数伝達関数の理論値を設定。
伝達関数を定義すると、この伝達関数を持つ撮影系に、任意の周波数特性を持つ波形を入力した場合のレスポンスが計算可能となります。この伝達関数として、著者が拡張した双曲線正割関数を用いています。この関数は V=(sech(A*W))^B の形をしていて、A, B は正の実数値です。この係数A, B によって、曲線がどのように変化するかを見るプログラム SOLITON.EXE も COLTDEMO.ZIP に含まれています。
- この伝達関数を持つ撮影系に、矩形波を入力した場合の出力を計算。
この結果をプロットしたのが最初の図です。
実際の測定では、検出器としてX線写真フィルムを利用しますので、写真フイルム特性曲線の数学モデルなどを使用して、写真濃度からフイルムへの露光量へ変換する必要があります。
- 項数を指定して、コルトマンの換算式を用いて伝達関数を計算。
計算に誤差がなければ、元の伝達関数と一致するはずですが、ここでは、項数を変えた場合に結果がとうなるかを見ることができます。指定可能な項数は25項までとなっています。
コルトマンの換算式は、級数展開式です。この級数展開は非常に収束が遅く、必ずしも項数が多ければ精度が高くなるわけではありません。
このプログラムも、ホームページ開設に伴い、Windows で動作するプログラムに書換えたかったのですが、現在のところ時間的な余裕がありません。とりあえず、手元にある PC-9821
Np を使用して動作だけは確認しました。懐かしい Roland
DG の DXY-880A ペンプロッタでプロッタ出力も確認しました。 |
| 仮定した伝達関数(実線)とその撮影系による矩形波のコントラスト (破線) |
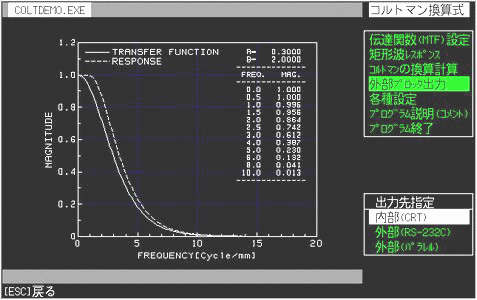 |
矩形波出力から伝達関数を計算
破線がコルトマンの換算式の第 3 項までの計算結果
実線は仮定した伝達関数
計算誤差がなければ両者は一致する |
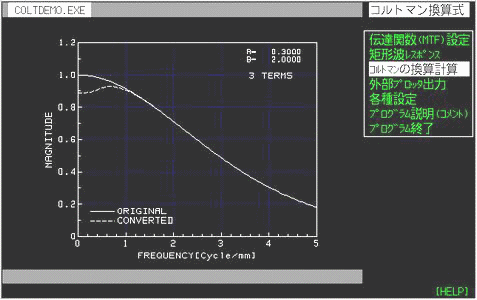 |
ダウンロードしたファイルを解凍したら、解凍したファイルを全て適当なフォルダに移動します。次に PC-9801 を MS-DOS モードで起動します。もし Windows 95/98 が動作していたら、MS-DOS で再起動して下さい。
- PC-9801 の MS-DOS プロンプトでは動作しません。
これは PC-9801 の仕様です。起動したら先程のフォルダに移動して、COLTDEMO.EXE を実行します。 |
電子回路や制御系等、正弦波の周波数の入力に対する応答が伝達関数です。
エックス線撮影系では、正弦波の値 (正弦関数の値) がエックス線の透過率ということになりますが、多くの周波数の正弦波チャートを用意しなければなりません。現実には無理があります。
正弦波を使用しない別の方法があります。それはインパルスという、数学的に無限小の幅の、つまり幅がない波形を使用する方法です。インパルスは、0 から無限大までの周波数の、同じ振幅の正弦波で表せますから、一回で伝達関数が求まります。光学系では、スリット法と呼ばれていますが、無限小の幅のスリットを実現するのは不可能なので、現実には、その系の伝達関数の結果に誤差がない程度のスリットを使用することになります。
制御系では、ステップ関数というものが使われることがあります。これは、光学系ではエッジ法に相当します。
MTF は、空間周波数における伝達関数の振幅特性のことです。周波数は正弦波の周波数のことですから、正弦波伝達関数、正弦波 MTF や矩形波伝達関数、矩形波 MTF 等の用語はあり得ません。もちろん、三角波 MTF とか鋸波 MTF 等と言うのもありません。
電子回路や制御系では、正弦波伝達関数とか矩形波伝達関数等の意味不明な用語は使われていません。伝達関数は伝達関数であって、伝達関数以外の何者でもありません。
|
[備考 1]
日本では、レスポンス関数という用語が使われていたことがありますが、現在は国際的に OTF (光学伝達関数) に統一されています。つまり、レスポンス関数は OTF のことです。。
したがって、正弦波レスポンス関数とか矩形波レスポンス関数と言うのはあり得ません。 |
[備考 2]
周波数に対する出力のコントラストの変化が振幅特性です。その意味で、振幅特性のことをコントラスト伝達関数と呼ぶことがあります。例えば「フーリェ変換の結果のコントラスト伝達関数は・・・」と言うように使うことがあります。
この場合のコントラスト伝達関数は、X 線撮影系では MTF のことになります。 |
用語という意味の関連では、CAD (Computer- Aided Diagnosis コンピュータ支援診断) は。シーエーディと読み、CAD (Computer Aided Design コンピュータ支援設計) はキャドと読みます。こうすることによって、同じコンピュータ関連用語でも、会話の中で区別がつくわけです。
医療関係者の方が「キャドを使っている」と話したら、一般のエンジニアの方は「医療施設関係の設計を手掛けているんだな」と思うかも知れません。
|
正弦波というのは不思議な波形です。正弦波は三角関数の正弦関数 (sin 関数)で表現する波形ですが、数学的にも不思議な波形です。
電子回路に正弦波の波形を入力すると、出力も正弦波の波形となります。周波数 (正弦波)
を変えても出力は正弦波のままです。
光学系や X 線作榮敬の入力に、これは透過率が正弦波状に変化すするチャートのことになりますが、この出力もやはり正弦波状となります。周期の異なる正弦波チャート、つまり空間周波数を変えても、やはり正弦波状になります。
ただし、周波数が高くなると出力の振幅は小さくなります。光学系や X 線撮影系では出力の強度差が低くなります。周波数に対してこの振幅の特性を表すことを「振幅特性」と言います。
もう 1 つの現象があります。正弦波の入力に対しては出力も正弦波になりますが、電子回路では出力に時間的なズレが発生します。この現象は空間周波数の場合も発生します。空間周波数では位置がずれることになります。
このズレを位相差といい、正弦関数の角度で表します。角度で表しますから、周波数が低い時は目立ちません。周波数に対して位相差を表した特性を「位相特性」と言います。
電子回路では、位相特性と振幅特性を含めて「伝達関数 (TF)」と言います。光学系や X 線撮影系では OTF ですが、その振幅特性のことを MTF と言います。
扇形 (楔形) のスリットを、円の中心に向けて配置したチャートを撮影した画像で、スリット像の強度が反転している画像を教科書、あるいは参考書で見たことがあるかも知れません。それは、この位相のズレが原因で起こります。
入力が正弦波ではない場合は、波形の周期が短くなると、出力波形は入力波形と同じにはなりません。例えば、入力を矩形波にすると、出力は、電子回路では矩形波とは似ても似つかない波形になります。光学系や X 線撮影系では矩形波と似た波形にはなりますが、矩形波ではなくなります。つまり、矩形波としては伝達されません。
入力と出力の波形が同じになるのは正弦波だけです。
1800 年代の初め、フランスの数学者・物理学者であるフーリェは、自身の熱伝導の研究において、どんな波形も三角関数の級数で表せることを示しました。
これをフーリェの級数展開式等と呼びます。フーリェの級数展開式の各項は周波数成分ですが、これを無限の周波数に拡張して、波形を周波数空間における値 (位相と振幅) とするがフーリェ変換です。
入力波形をフーリェ変換して。伝達関数が分かっていれば出力は計算できることになります。もちろん、周波数空間における計算ですから、実空間としての波形にするには計算が必要です。この計算を逆フーリェ変換と言います。逆フーリェ変換がフーリエの級数展開式に相当します。
当然、入力波形と出力波形のフーリェ変換から伝達関数を計算することもできます。
我々は普通にフーリェ変換を使用し、伝達関数という用語を使用していますが、改めて考えてみると、正弦波は実に不思議な波形で、自然界における基本的な波形と言えます。
物理・工学のあらゆる分野でこの正弦波の性質が使用されています。 |
コルトマンの換算式を使用すると、周波数解析をしなくても X 線撮影系の伝達関数の MTF を計算することができます。
上の正弦波の不思議で述べたように、伝達関数分かっていれば、入力波形に対する出力波形を計算することができます。入力波形が矩形波の場合、矩形波の周期、つまり、矩形の間隔が短くなると出力は矩形波とはなりませんが、矩形波と似た波形になり、波形の振幅比が理論的に計算できます。
矩形波の周期に対する振幅比の変化は、当然、伝達関数によって変わります。
出力の振幅比の変化が伝達関数によって変わるのですから、理論的には、矩形波の周期と出力の振幅比の関係から伝達関数が計算可能ということになります。この矩形波の周期と出力の振幅比の関係から MTF を計算する理論式がコルトマンの換算式です。
矩形波の場合も周期が長い時は、出力波形の山と谷の部分における強度に違いが現れません。したがつて、周期の長い矩形の出力の強度は、矩形羽チャートの X 線の透過率を反映していることになります。これを入力として扱います。矩形波の各周期における、この入力としての強度 (あるいはコントラスト) の変化を測定します。
コルトマンの論文は 1954年の Journal of the Optical Society of America, Vol. 44 に掲載されています。タイトルは The Specification of Imaging Properties by Response to a Sine Wave Input となっています。
以下はその論文の Abstract の部分です。
|
| The imaging properties of an optical system can be in many cases completely specified by a function of a single variable. A convenient function is the response to a sine wave test pattern as a function of “frequency,” i.e., lines/mm. The difficulty of experimentally providing such a test pattern can be avoided by measuring the response to a square wave (bar pattern) and calculating by a simple formula the corresponding sine wave response factor. The convenience of the sine wave response factor in calculating system performance is illustrated by application to a fluoroscopic imaging system. |
[備考]
電子回路では電子回路を通過した時、一般的な光学系では主にレンズを通過した時の入出力の伝達特性 (位相、振幅) が伝達関数です。
X 線撮影系では、X 線撮影系のシステムの特性です。この特性の要因は、X 線の発生源である X 線管の焦点の構造や増感紙等の構造です。 |
|